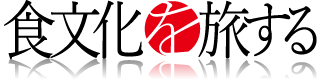第2回(全4回)
ヨーロッパ軒から始まる福井のソースカツ丼
福井市のソースカツ丼を語るうえで、「ヨーロッパ軒」が唯一無二の存在であることは言うまでもありませんが、それだけではなくソースカツ丼の発祥のお店であり、今や国民食ともいえるカツ丼の発展に大きな影響を及ぼしたと言えます。ここで、地元で「パ軒」と呼ばれ親しまれている「ヨーロッパ軒」の歴史を紐解きながら福井市のソースカツ丼文化を考えてみたいと思います。
「ヨーロッパ軒」創業者の高畠増太郎氏は1906(明治39)年にドイツに渡り、ベルリンの日本人倶楽部で6年間修行して1912(明治45)年に帰国し、1913(大正2)年東京の早稲田鶴巻町でお店を開きました。その後、1917(大正6)年に神奈川県横須賀市追浜に出店しましたが、1923(大正12)年の関東大震災で故郷の福井に戻り、翌1924(大正13)年福井市の片町通りに現在の「ヨーロッパ軒総本店」を開業しました。
当時、料理修行でヨーロッパに渡るというのはかなり稀なことで、「天皇の料理番」として知られる秋山徳蔵氏とはドイツ留学の同期生とのこと。それまでなかった料理を発想した高畑氏はフロンティア精神に溢れた想像力豊かな方だったのかもしれません。

洋食を広めるソース
さてソースカツ丼は、ドイツでウスターソースと出合い、このおいしさを日本に広めたいという高畠氏の思いから始まりました。日本人の味覚に、そしてご飯に合うようソースを工夫し、当時人気になり始めた洋食のカツレツにソースを絡めてどんぶりにのせるというのは、斬新な発想だったでしょう。これを東京の料理発表会で披露し、ソースカツ丼はお店のメニューとなりました。料理発表会はコンテストのようなものではなく、東京都内の大学の講堂のような場所で行われたということです。
大正時代の洋食のカツレツは、現在もドイツで人気の「シュニッツェル」の様に薄くたたいて少ない油で揚げ焼きしたカツレツです。ドイツで修行した高畠氏がこのシュニッチェルでソースの美味しさを伝えようとしたのであれば、ある意味でソースカツ丼の主役はカツではなく、ソースだったと言えるのではないでしょうか。
ちなみに創業時のソースは高畠氏が考えたレシピをブルドックソースに相談し、作ってもらっていたとのこと。福井に移ってからはイカリソースと同様に取り組んだそうです。洋食の人気が根付き始めたころ、ソースを自前で作るのは至難の業で、今では考えられないような小ロットでも、日本の洋食文化の黎明期をソースメーカーが応援していたからこそ、洋食は和洋折衷を代表する日本食として定着したのでしょう。

起源の西洋料理
日本のカツレツはフランスの「コートレット」が、英語圏から「カットレット」として伝わり、なまって「カツレツ」になったという説が有力です。一方ドイツの「シュニッツェル」はイタリアの「コトレッタ」起源説が有力で、日本では「ウインナーシュニッツェル」(ウイーン風カツレツ)、「コトレッタ・アラ・ミラネーゼ(ミラノ風カツレツ)」として、ドイツ料理、イタリア料理のお店に受け継がれています。「コートレット」も「コトレッタ」も食材の「仔牛の骨付きロース肉」を指しますが、由来の料理は玉子や小麦粉、パン粉を使い、油で揚げ焼きするような料理法を指すようになりました。

「ウインナーシュニッツェル」は牛肉のカツレツですが、ドイツの「シュニッツェル」は現在では豚が一般的です。実は「ヨーロッパ軒」のソースカツ丼の誕生時は牛肉を使っていたそうです。豚肉を使用するようになったのは福井に本店を移した時期で、大正時代に流通が広がったため、豚肉のソースカツ丼を出すようになったそうです。
ヨーロッパ軒はのれんやメニューに「西洋御料理」というキャッチフレーズ的な言葉が記載されており、メニューの表紙には、牛をモチーフにしたマークが描かれています。
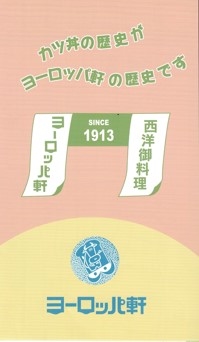

豊かなバリエーションのソースカツ丼
創業した大正初期は東京でも洋食といえば豚肉ではなく牛肉という時代でした。ちなみにメニューにはビーフカツ丼も載っており、昔からあるカツ丼としては全国的にも珍しい牛肉のカツ丼を食べることができます。
ソースカツ丼が根付いている福井市ですが、ヨーロッパ軒ののれん分けを中心に広がっていきました。のれん分けのお店のメニューにはオリジナリティもありますが、豚肉のソースカツ丼と既述のビーフ他、エビやメンチ、チキン(総本店にはなし)などのバリエーションがあります。 「ヨーロッパ軒」の歴史から、福井のソースカツ丼文化をより深く知ることができるのではないでしょうか。