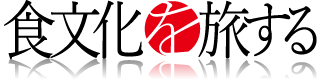山梨県は甲府盆地を中心に、北は八ヶ岳、西は南アルプス、南は富士山という山がちな地域と、急峻な山が多くほとんど平地がない東部の郡内から構成される。標高が高かったり、寒暖差の激しい盆地だったりで、特に冬の寒さが厳しい。また、郡内など平地が少ないことから米作に適さない気候風土だ。そんな山梨の冬を代表する味がほうとうだ。

米作に適さない山梨県山間部で古くから盛んだったのが養蚕だ。養蚕に不可欠なのが、蚕(かいこ)の餌となる桑の葉だが、桑の収穫が終わった畑では、米の代わりとなる主食として麦が栽培されていた。長野のそばや、南部地方のせんべい汁など、米がとれない地域では、米に代わる炭水化物の摂取を目的とした郷土料理が食べられていることが多い。麦を麺にして、季節の野菜といっしょにみそで煮込んだほうとうもそんな料理の一つだ。

そもそもは、中国からもたらされた「饂飩(はくたく・はうたう)」が料理名の語源といわれている。それを武田信玄が野戦食として用いたことから、甲州地方に広く根付いたという。信玄公が、自分の刀を使って食材を切ったことから「宝刀(ほうとう)」と名付けたとの説もある。富士川沿岸の峡南地域では「のしいれ」「のしこみ」とも呼ばれている。

粉にした小麦を麺に打つのはうどんと同様だが、その最大の違いは、塩を加えないこと。しかも、打った後寝かさず、すぐに麺切りして調理する。うどんは、寝かせることで麺に弾力性を持たせたり、麺の中に残った気泡を逃がしたりするものだが、ほうとうの麺にはその課程がない。

また、煮込みうどんなどでも、一度茹でてから煮込むことが多いが、これは生地に残った塩分を抜く調理過程でもある。なので、ほうとうの麺は下ゆでせずに、そのまま煮込むことができるというわけだ。そして、生麺を煮込むということは、打ち粉もともに煮込むため、汁にとろみがつくという特徴がある。

調理法としては、煮干しなどでとっただしを沸騰させ、そこにほうとうには欠かせないかぼちゃなど季節の野菜やきのこなど、硬いものから切って順に入れていく。具材に火が通って柔らかくなったら、ほうとう麺を入れる。ここで、半分だけみそをだしに入れて、しばし煮込む。麺が透き通ってきたら、残りの味噌を加えて味をととのえ、煮立ったらねぎを入れて火をとめ、蓋をして2~3分蒸らす。肉などは好みで入れて良い。決まった肉はない。

実際に地元のお店でほうとうを食べてみよう。まず訪ねたのは、甲府駅前をはじめ山梨県内を中心に9店舗を展開する「小作」だ。ほうとうと言えば、地元で真っ先に名前が挙がる有名店だ。日曜日の開店時間に合わせて店を訪れたが、すでに開店前に、店頭には行列ができていた。

人気ナンバーワンというかぼちゃほうとうをいただいた。火を通すと独特の甘さとほっくりした食感を生み出すかぼちゃは、ほうとうに欠かせない食材の一つだ。麺はもちもちの食感を出すべく試行錯誤を重ね、粉の配合をほうとうに最適な割合で製麺したオリジナル麺だ。

秘伝のだしは、野菜をベースにしたもの。ほうとうのために調合されたオリジナルのみそで味付けをする。そして、大鍋ではなく1人前ずつ鉄鍋で煮込むのが「小作」のこだわりだ。1人前ずつ調理するので、煮込み時間はさほど長くはない。

そのため、生麺を煮込むにもかかわらず麺の角がしっかり立っている。野菜も煮崩れてはいない。個人的に、ほうとうは麺も具材もどろどろというイメージを持っていたのだが、それが見事に覆された。かぼちゃ特有の甘さにもくどさがない。煮込みうどんにもかかわらず、麺や具材、スープが渾然一体というよりは、それぞれが持ち味を存分に発揮しつつ、ほうとうとしてのマリアージュを醸し出している、そんな印象を抱いた。

念のため、場所を移してもう1軒、ほうとうを賞味した。訪れたのは、山梨市駅前に本店を構える「歩成」だ。かつて、ほうとうの味を競うイベントで3連覇を達成したとのこと。同店のほうとうは、かぼちゃのペーストを加えた黄金味噌に、あわびの肝のペーストと、京都風のだしをあわせたもの。これをカセットコンロを使い、客の目の前で煮込んでいく。

野菜やきのこなど、具材の量は「小作」に勝る。また、自慢の黄金味噌は、実に深い味わいだ。麺も具材もやはり煮崩れてはおらず、洗練されたスープも相まって実に上品な味に仕上がっている。大鍋でごった煮にする素朴な料理という、それまでのほうとうのイメージが大きく覆された。

さらにテーブルに用意された辛みそが実にいい仕事をしてくれる。場所柄、吉田うどんで使われるすりだねかと思ったが、さほど辛味はない。すりだねとは別もので、店のオリジナルという。みそのこくとほんのりとした辛さが、黄金味噌のスープの味をさらに膨らませてくれる。

では、どろどろに煮込んだほうとうのイメージは幻だったのか? 調べていくと、家庭では大鍋で家族の人数分を一度に調理するのが一般的で、しかも食べ残しを翌朝食べたりするのだそうだ。温め直せば、余計どろどろどろになるだろう。どろどろは家庭で食べるほうとうだったのだ。一方で、家庭でもどろどろではないほうとうが食べたい場合、麺を別鍋で茹でた後、一度冷水で締めてから煮込むとドロドロになりにくいという。いずれにせよ、どろどろが好きな人は、生麺を買ってきて自分で煮込むといいのだろう。