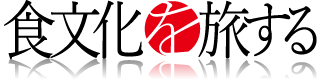和食の味の要・だし。その基本は、かつおと昆布というのが一般的だ。北海道が主産地の昆布は北前船の航路、すなわち日本海沿岸から瀬戸内海を通って大阪湾までの地域で多用され、海の荒い太平洋沿岸では、かつおを多用することが多い。そんなだしの歴史は縄文時代に遡る。火を使うことを覚えた人類は、食材を煮て食べるようになり、加熱の過程で食材のうまみが煮汁に染み出すことを発見した。

そんなだしが、記録に残されるようになったのは、約1300年前の奈良時代のこと。かつおについては、かつおを干し固めた「堅魚」や煮てから干し堅めた「煮堅魚」、煮汁をさらに煮詰めて調味料とした「煮堅煎汁」といった記述が、租庸調と呼ばれる朝廷に納める税として記録されていた。

かつおだしの基本は、現在ではかつおぶしだが、実はかつお節が誕生するのは江戸時代に入ってからだ。加熱や乾燥で腐敗の速度を遅らせる一方、塩蔵、つまり塩漬けにしたうえで乾燥させ、保存性を高めることを人類は編み出した。これが、かつお節の原型と言われ、現在でも静岡県西伊豆町田子地区だけでつくり続けられている潮がつおだ。

平城京から出土した木簡には、田子から「調」として「荒堅魚(あらかつお)」を平城京に納めたと記録されている。これが、潮がつおではないかと考えられている。かつおぶしは、高温多湿を避ければ1~2年は美味しく食べられる。塩蔵とは言え、潮がつおとは比べものにならない保存期間の長さだ。それが故に、かつおぶしの誕生をきっかけに潮がつおが日本から姿を消すことになった。ではなぜ、田子地区にだけ潮がつおが残ったのか。

それは田子の生活習慣に潮がつおが欠かせない存在だったからだ。田子は、そもそもかつお漁が盛んだった漁師町で、藁で飾つけた潮がつおを軒先に吊し、航海の安全と豊漁を祈願していた。正月には、軒先の潮がつおを船主が、雇用のしるしとして船員たちに分け与えて新年を祝う習慣もあった。なので、潮がつおの別名は「正月魚」。これが、かつお漁衰退後も、生活習慣として残り、潮がつおも継承されていったというわけだ。

田子で潮がつおづくりを続けるカネサ鰹節店では毎年、正月を前に潮がつおづくりの体験イベントを開催している。11月末に同店を訪れ、潮がつおの仕込みを体験、約1カ月かけて熟成・乾燥させた後に、年末を前に自宅にできたての潮がつおが届くというしくみだ。講師は同店の5代目にして、潮がつおの継承はもちろんのこと、世界を股にかけてかつおぶしの魅力を伝え続けるかつおぶし界のカリスマ・芹沢安久さんだ。

歴史を感じさせる工房で、まずは芹沢さんが潮がつおとかつおぶしの歴史について語る。誕生の歴史から始まり、製法、保存法、美味しい調理法に至るまで、様々な資料と、なまりぶしや燻蒸させた荒節、荒節にカビつけをして発酵させ徹底的に水分を抜いた本枯節などを手にていねいに解説する。

座学が終わったら実体験だ。参加者がそれぞれ、自分で潮がつおの下ごしらえをする。芹沢さんの手さばきをお手本に、かつおに包丁を入れていく。まずはお腹だ。胸のあたりから、魚体下後方に空いた穴に向かって切っていく。すぐに内臓が見えてくる。

そうしたら次に、えらに手を入れる。えらには指がそのまま入るので、えらを皮から剥がすようにして引っ張る。えらが外に出てくると、顎の下の部分がくっついているので、ここは包丁を使って切る。それを力一杯引っ張り出すと、えらが内臓と一緒につながって外に出てくる。これで、内臓がきれいにとれるというわけだ。

内臓を取り出したら、一度きれいに洗う。お腹の中には血がたまっているので、それを洗い流す。そして、頭の部分に手を突っ込み、目玉を潰して掻き出す。目玉には水分がたくさん残っているので、目玉をきちんと取らないとそこから腐敗しやすくなるからだ。

塩漬けする前に、魚体にしっかり塩が馴染むよう中骨から左右の身を剥がす。内臓がなくなった部分からお腹の中に包丁を差し入れると、必ず中骨の左右どちらかに包丁が入ることになる。中骨の位置を確かめながら、身を中骨から切り離していく。その際に背中まで包丁を貫通させてはいけない。そこから塩が出てしまうからだ。頭と尻尾を入れ替え、頭方向にも尻尾方向にも中骨から切り離す。

片側が終わったら、同じ手順で残った側も中骨から切り離していく。いちどに切る必要はない。何度も包丁を入れながら、背中・尻尾・頭がつながったままで、魚体が袋状に3枚に下ろされることになる。お腹の中に十分な空間ができあがったら、最後、そこに塩を詰めていく。

たっぷりの塩を、かたまりを粉々にしつつお腹の中に入れていく。その際、ヘラを使って、塩を魚体の下の方までゆすり入れていく。魚体の隅々まで塩を詰め込む。お腹、そしてえらが塩でぱんぱんになったら、表面にも塩をすり込もう。塩をたっぷりとまんべんなく詰め込むのが潮がつおづくりの基本だ。

塩を詰め終わったら、こぼれ出ないように切って塩をつめた部分を上にして下ごしらえしたかつおを並べていく。これを「カネサ鰹節店」で約1カ月かけて熟成・乾燥させれば、潮がつおのできあがりだ。熟成・乾燥を待ってクリスマスに完成した潮がつおが自宅に届いた。

かつおはそもそもだし取りに使われるなど非常にうまみが強い魚だ。潮がつおは、そのまま焼いて食べても日本酒のいいつまみになる。また、塩味が非常に強いので、調味料としても多くの料理に応用できる。さらに塩抜きすれば、うまみの強い食材としても様々に食べられる。

西伊豆町では、潮がつおをなまり節や削り節とともにまぜうどんにした西伊豆しおかつおうどんをご当地グルメとして全国に発信している。お近くにお越しの際には、ぜひカネサ鰹節店に立ち寄り、潮がつおを手に取って、食べてみることをお薦めする。