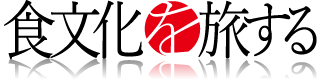うなぎと言えば高級魚の代名詞。海で産卵・孵化し、淡水にさかのぼってくる「降河回遊(こうかかいゆう)」のため、海なし県も含めて全国で広く食べられている。その歴史は古く、縄文時代の貝塚からうなぎの骨が出土するほど。「万葉集」にもうなぎを題材とした歌があり、室町時代には蒲焼きも登場。しかし、広く庶民に食べられるようになったのは江戸時代以降のことだ。特に江戸など都市部での人口増加に伴い、滋養強壮に効果のある魚として人気を博すようになったという。いずれにせよ、その頃から一貫して、うなぎは高級魚として重宝されてきた。

しかし、そんな高級魚・うなぎを庶民の食として食べる地域がごくわずかだがある。以前紹介した三重県津市では、うなぎの産地だったこともあり、藩主・藤堂家は、藩士たちに地元の名物であるうな丼を食べて精をつけ、つとめに励むよう奨励したことからうな丼がハレの日ではなくケの日の食として定着している。そう、キーワードは産地だ。今回紹介する、ケの日のうなぎであるぼくめしも、静岡県西部に広がる養鰻業者のまかないとして生まれたものだ。

うなぎ養殖の歴史は、明治時代に遡る。東京で川魚商を営み、うなぎの研究をしていた服部倉治郎が始めたものだ。1897(明治30)年に、愛知県へ向かう汽車から浜名湖を目にした倉治郎は「鰻養殖に最適な場所」とそのまま汽車を降りた。そもそも天然物のうなぎが穫れる湖のため、養殖用の幼魚の入手も容易で、養殖池に適した広い土地もあることなどから、1900(明治33)年に、ここでうなぎの養殖に着手する。以来、浜名湖を中心とする静岡県西部、愛知県東部はうなぎの一大産地として発展していく。

日本養鰻漁業共同組合連合会の2022年の統計によると、うなぎ収穫量は、全国で19,167トン、県別では鹿児島県が7,858トン、ついで愛知県が4,205トン、宮崎県が3,574トン、静岡県は2,365トンとなっている。愛知・静岡に対し鹿児島・宮崎の収穫量は倍近い。しかし、九州産うなぎの歴史は実は浅い。鹿児島のうなぎ生産の中心は大隅半島だが、大隅地区養鰻漁業協同組合が設立されたのは1972(昭和47)年、昭和47年のことだ。それまでは、長く東海地区が養鰻の中心だった。長い歴史を持つだけに、食文化の面にも深く足跡を残している。そのひとつが、ぼくめしという訳だ。

ぼくめしは、炊きあがったご飯にうなぎとごぼうを煮たものを合わせた混ぜごはん。その料理名は太い杭の「木杭(ぼっくい)」が由来とされている。静岡県の主なうなぎ養殖地は、浜名湖周辺と大井川流域の2カ所。そのひとつ、県中央部で島田市、牧之原市、焼津市に囲まれた吉田町は、焼津市との市境を流れる大井川で洪水が頻発、稲が育たなくなった水田を養鰻池に変換、うなぎ養殖を始めた。広い露地池のため、逃げ出すうなぎが多く、再び捕まるまでの間に大きく太りすぎてしまい、出荷に適さなくなったうなぎも多かったという。そんな太すぎるうなぎ、つまりは「木杭(ぼっくい)」を、養鰻作業の際のまかないや家族の夕食として食べるようになったのがそのルーツといわれている。

作り方は、シンプル。ごぼうを小さくささがきにして、水にさらしてアクを抜き、茹でる。うなぎは、蒸して、細かく切る。これを砂糖、しょうゆ、みりんでを加えて、弱火でトロトロと汁がなくなるまで煮る。煮上がったら白いご飯と混ぜ合わせ、錦糸卵や大葉、いんげん、ゴマなどを加えれば完成だ。

実際に、ぼくめしを食べてみよう。その歴史的経緯から、ぼくめしはまかないや家庭のご飯として食べられてきたため、そもそもお店で食べるものではないようだ。吉田町を中心に提供店を探したが、なかなか見つからない。家庭での消費も想定して、スーパーの惣菜売り場なども探したが、うなぎの絶滅危惧もあり、うなぎそのものが高価になったことから、今は家庭でもあまり食べられなくなっているようだ。

みつけた提供店は、養鰻場の敷地内で営業する「うなぎの天保」。多くの客が4400円の上うなぎ重や3900円の上うなぎ丼を頬張る中で、2700円のボクめし丼を注文した。「池番の賄いめし」とメニューには記載されているが、うなぎ屋だけに漬物、肝吸い物付きで運ばれてきた。

うなだれご飯のように、ご飯全体にしっかり味が染みたところに、アクセントとして大葉と錦糸卵がのせられ、ごまも散らされている。うなぎもごぼうも「保護色」のご飯の中に紛れてしまっていて、その存在が判然としない。スプーンが付いていたので、山椒をかけてスプーンで掻き込んで食べた。

ちょっと甘めの味付けで、食が進む。口の中に入れてみると、感覚的にうなぎの味と存在感がごぼうのそれとほぼ同等だった。もちろん、うなぎ重やうなぎ丼に比べれば、うなぎの大きさは圧倒的に小さい。とはいえ、うなぎとごぼうの味と食感が、ご飯にちょうどいいのだ。食べた満足感は、重や丼に引けを取らない。

「うなぎの天保」ではパック入りの「うなぎボク飯の素」も販売されている。すでに煮込まれた具がパック入りになっている。これを炊きたてのご飯に混ぜれば、家庭で簡単にぼくめしが食べられる。「うなぎの天保」のホームページから通販でも取り寄せられるので、興味のある人は取り寄せてみてはいかがだろうか。

必死でネット検索した結果、もう1軒、ぼくめしの提供店を発見した。浜松の駅弁としても有名なうなぎ弁当で知られる「自笑軒」の「花べんとう『ぼくめし』」だ。地域の特産品やお米の地産地消を目的に、地元の生産者と協力して開発したお弁当だという。ぼくめしに、鶏モモ肉のゆかり焼き、青のり入り海老てんぷら、ほうれん草の和え物&遠州灘産シラス干し、うま煮、さらに静岡らしくわさび漬も添えられている。

ぼくめしは、「うなぎの天保」に比べうなぎも控えめで、ミックスベジタブルも入るなど手軽さが強調されているが、今ではなかなかおめにかかれないぼくめしを1000円という価格で手軽に食べられるのはうれしい。浜松駅や掛川駅構内に「自笑亭」の販売ブースがあるので、現地を訪れた際には、ぜひ味わってみてほしい。