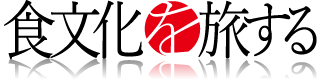四国のうどんというと誰もが、香川県のさぬきうどんを思い浮かべることだろう。しかし、愛媛県松山のアルミ鍋で食べる鍋焼きうどんや大きなたらいでうどんを食べる徳島県阿波市のたらいうどんなど、さぬきうどんに限らず、各地で多彩にうどんが食べられている。そんな、四国のご当地うどんの一つに徳島県鳴門市のうどん、鳴ちゅるうどんがある。

瀬戸内海に面する鳴門市は、昭和後期に至るまで製塩業が盛んで、あちこちに広大な塩田があった。塩づくりは重労働、そこで額に汗して働く人たちのために、柔らかく食べやすい食事として提供されていたのがうどんだ。この鳴門ならではのうどんを、2000年代に入り、徳島県の写真家・中野晃治氏が「鳴ちゅる」と命名、「鳴門のちゅるちゅるうどん探訪記・鳴ちゅる」を出版。その後、鳴ちゅるうどんとも呼ばれるようになった。ちなみに、大分県でチェーン展開する「鳴門うどん」は、鳴門のうどんとは別ものだ。

最大の特徴は、さぬきうどんとは真逆ともいえる短く柔らかい麺。しかも不揃いだ。短く柔らかいために、小さな子どもでも「ちゅるちゅる」と食べられるというのが、鳴ちゅるうどんの語源だそうだ。

だしは、煮干しを使ってあっさり仕上げるのが鳴門流。いりこの煮干しを使うところはさぬきうどんと共通しているが、天ぷらを添えたり、釜玉にしたりとはこれまた対照的に、トッピングはネギと刻んだ油揚げのみと非常にシンプルだ。鳴門わかめが名物でもあり、わかめやちくわが入ることもある。シンプルさは食べ飽きず、食欲がわかないときや二日酔いでも食べやすいというメリットもある。

実際にお店で鳴門のうどんを食べてみよう。まず訪れたのは「舩本(ふなもと)うどん本店」。創業40年、店の外観は老舗を思わせる装いだったが、暖簾をくぐってみると、その大衆的な価格とシステムに驚かされた。デフォルトメニューの鳴門うどんは、なんと税抜きで380円。大でも530円だ。これにわかめやちくわなどのトッピングを加えていく。

デフォルトの具は、油揚げと薬味のネギのみだった。つゆは、いりこだしを最大限生かしたシンプルな味付け。確かにこれなら二日酔いでも気にせず食べられそうだ。油揚げのみというこれまたシンプルなトッピングもいい。

麺はとてもソフトな歯触り。ただし、九州うどんの柔らかさともまた違う。不揃いな形状もあり、それなりに食感がある。とはいえ、かなり柔らかいので、するするというか、ちゅるちゅると一気に食べてしまう。量も軽めだ。ちゃんとしたお昼として食べるなら、大の方がおすすめかもしれない。

今回はここに鳴門かきあげを追加してみた。別皿で運ばれてきた。よく目をこらしてみると、大ぶりに刻まれたサツマイモが入っている。鳴門金時だ。鳴門金時は、鳴門海峡、旧吉野川、吉野川などの砂地で作られるさつまいものブランド。上質な甘みが特徴だ。徳島らしい食材を使うことで、鳴門らしさを演出しているようだ。鳴門金時だけの天ぷらもある。

すっきりとしたいりこだしにかき揚げをのせると、一気に油が広がる。あっさり、おやつ感覚の鳴門のうどんが、コク深い、ヘビーな味わいに変わる。とはいえ、いりこだしを一気に吸い込んだかき揚げの衣もまた美味しい。軽食ではなく、腹の足しとして食べるのであれば、やはりトッピングを加えた方がよさそう。

各店で幟を立てるなど、2000年代に入って鳴ちゅるうどんのブランド化に取り組んでいるようだが、実際のところメニュー名は「鳴ちゅるうどん」ではなく、「鳴門うどん」や「わかめうどん」などになっているケースが多かった。鳴門公園内にある各飲食店も同様で、「木下商店」では「わかめうどん」となっていた。

しかし、あっさりいりこだしに、ソフトな食感のうどんは共通だった。トッピングは鳴門名産のわかめと油揚げ、そして薬味のネギだ。一方で「木下商店」では、麺にもわかめが練り込まれていた。やはり、食感同様、腹持ちも軽めでお昼前やおやつの「虫押さえ」にぴったりのうどんと言えた。

観光地のドイツ村に隣接する「道の駅第九の里」のお土産コーナーでは「鳴ちゅるうどん」を標榜するパッケージも販売されていたが、正直なところ「鳴ちゅるうどん」で店を探すとけっこう閉店していたり、販売を取りやめているケースも多かった。とはいえ、鳴門で伝統的にソフトな食感でシンプルなうどんが食べ続けられてきたことは間違いない。「鳴ちゅるうどん」というネーミングにあまりこだわらず、伝統的な「鳴門のうどん」として店を探し、食べ歩くのがベストかもしれない。