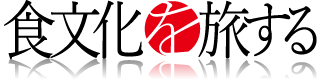料理には欠かせない塩。海から遠い内陸の国などでは岩塩も使うが、島国日本では、海水から塩を作るのが一般的だ。かつては海水を様々な方法で塩分濃度を上げた上で火に掛け、塩を取り出していた。しかし、気候や地形、海の状態によって、地域ごとに製塩方法は異なっていた。

瀬戸内海や東京湾など、波の穏やかな内海で行われていたのが「入浜式」と呼ばれる製塩法だ。潮の満ち引きを利用した方法で、遠浅の浜に作られた塩田に砂を撒いておき、そこに潮が満ちると海水が入り、その後潮が引くと塩田には海水が残る。引き潮の間に太陽光で水分が蒸発すると、塩田には濃度の高い海水を含んだ砂が残る。この砂をかき集め、もう一度海水で洗うと、塩分濃度の高い海水ができあがる。これを火に掛けて水分を飛ばせば塩ができあがる。作業効率のいい製塩法だ。

しかし、瀬戸内の赤穂や東京湾の行徳といった、外洋の潮流の影響をほとんど受けない地域では可能な製塩法だが、日本海など常に荒波を受ける海岸では、せっかく塩分濃度の高い海水を含んだ砂が、高い波で洗い流されてしまう。

ではどうするか。波の届かないところで砂に海水を含ませ、天日干しにした。これが「揚浜式」だ。

海に面した岩場などの上に塩田を作り、そこに海水をくみ上げ、海水を撒くのだ。海から高台まで海水をくみ上げるのも、そこで海水を撒くのも、基本は人力だ。しかも、広い塩田に均等に、幅広く海水を撒く必要がある。ともに大変な重労働だった。

しかし、機械や物流が発達していなかった時代は、それだけの重労働をしてもなお、瀬戸内海や東京湾から塩を運ぶより採算性が高かったと言うことだ。

限られた地域だが、さらに生産性の悪い方法で製塩していたところもある。リアス式海岸など、海から近い平地がほとんどなかった地域では、海水をくみ上げ、塩分濃度を上げずに、そのまま火に掛けた。「直煮(じきに)」と呼ばれる製塩方法だ。塩分濃度の低い海水を火に掛けるため、大きな釜が必要で、燃料費もかさむ欠点がある。

三陸海岸の野田村では、この「直煮」で製塩していた。背後にそびえる北上山地で砂鉄がとれたことから鉄器が手に入りやすかったこと、そして、近隣は未開の森林が多く、燃料の薪にも困らなかったことが「直煮」を選択した理由だ。同地域で鉄器が手に入りやすかったことは、名産の「南部鉄器」からもうかがい知れる。

近代に入ると、製塩法も機械化される。そんな中で誕生したのが「流下式」だ。海水をポンプでくみ上げ、竹の枝などに滴らせる。長時間かけて滴ち落ちる間に風にさらされ、塩分濃度が上がる仕組みだ。ただし、日本海側など雪の多い地域では、積雪で施設が壊れるなど、「流下式」は適さなかった。

その後、イオン交換膜で海水の塩分を濃縮する方法が編み出され、気候や風土に影響されずに製塩できるようになると、こうした昔ながらの製塩法の多くが廃れてしまった。しかし、昔ながらの製塩法はミネラルを豊富に含むなど品質に優れたものが多く、ブランド塩として、現在でも昔ながらの製法で塩を作るケースがある。

さらに、原料となる海水によって成分も異なり、製塩法により結晶の形も違ってきたりする。特に、塩の専売制度が廃止されて以降は、各地域が伝統的な製塩方法を生かし、それぞれ個性をもった塩を作り、販売するようになった。調理のプロが塩にこだわり、産地やブランドを選ぶのはこのためだ。

産地や製法の違う塩を実際に食べ比べてみると面白い。味の違いだけでなく、結晶によっては溶けるまでに時間がかかったり、舌触りが違ったりして、それだけで味わいが違ってくる。様々な塩を自分の舌で確かめ、使う料理に適した塩を選ぶと、料理の味いもさらに広がること請け合いだ。