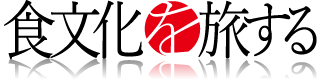岩手県の北部は、旧南部藩の領地。県南部の60万石を誇った伊達藩とは違い、夏の気温が上がらず、米作には適さなかった。このため、米にかわり塩で年貢を納めていた。南部藩の藩都は盛岡。内陸の地だ。年貢のための塩は太平洋岸・三陸の野田で精製され、陸路で盛岡まで運ばれた。この塩を運んだ「塩の道」のルートには、特徴的な食文化が点在する。とうふだ。

盛岡市は、とうふ消費金額(1世帯当たり)が、2019年の家計調査で全国の県庁所在地の中でトップ。過去にも常にランキング上位に入るなど、全国でも有数の「とうふ好き」のまちとして知られる。盛岡など、岩手県北の店頭で見かけるとうふの大きさは、関東人なら驚くほどのビッグサイズだ。

一方、塩の産地、野田のすぐ北にあるまち、久慈市の名物料理はとうふ田楽だ。みやげ物屋はもちろん、スーパーの店頭でも、串刺しにして味噌を塗り、炭火でとうふを焼いている光景にでくわす。串のままほうばるのはもちろんだが、大ぶりなとうふ田楽をいくつもパック入りにして売ってもいる。

久慈から少し内陸入った場所にあるジンギスカン店。皿いっぱいに盛られた羊肉にはとうふが添えられている。北海道はじめ、長野県や千葉県など、各地にジンギスカンで知られるまちは点在するが、鍋といいつつ実は「鉄板焼き」のジンギスカンにとうふが入るのは珍しい。

鍋物にとうふはつきものだが、岩手県北はちょっと勝手が違う。盛岡の北に位置する旧玉山村(現在は盛岡市玉山区)には、名物のモルモン鍋がある。具はホルモンとキャベツととうふのみ。加水はせず、キャベツと豆腐の水分だけでホルモンを煮込む。水分が沸騰し始めた鍋を見ると、ホルモン鍋というより、とうふ鍋と呼びたくなるような見た目だ。

塩の道の沿道でこれほどまでにとうふが食べられているのには訳がある。ご存知の通り、とうふは大豆から搾った豆乳をにがりで固めたものだ。では、にがりとは何か。製塩の過程で、海水を煮詰めた後に残る塩化マグネシウムを主成分とするミネラル分を多く含む液体だ。

現在でこそ、遠心分離機で水分を除去して塩を作るが、江戸時代にはそんな便利なものはない。生乾きのまま塩を俵に詰め、牛の背中に乗せて盛岡まで運んでいた。野田と盛岡の間には北上山地がそびえる。険しい山道を、歩みこそ遅いが、力強く登る牛が、塩俵を背負って、ゆっくりと時間をかけて盛岡まで運んだ。その間に、残されたにがりは、俵に染み込んでいく。これがとうふの原料となり、沿道で多くとうふが食べられるようになったという。

コールドチェーンのなかった時代、人々は手に入りやすい食材を工夫して食をつないだ。今に食べ継がれている郷土食の、名物料理の多くには、そうした、その土地の暮らしや気候が映されたものが多い。なぜそこにその味があるのか? そこには、歴史と人々のくらしの知恵が密接に関係している。