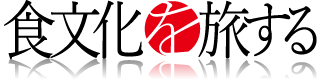移住すると決めて住まいを探すため、何度も東京と郡山を行き来した。何度目の郡山だったか、郡山駅で駅弁売り場を覗いたら「海苔のりべん」というものがあった。これまで全国を旅して行く先々でたくさんの駅弁を食べたが、のり弁の駅弁を見たのは初めてだった。

のり弁は持ち帰り弁当の定番であり、コンビニ弁当の一角を占め、しかも低価格帯という印象だった。しかしそののり弁は1300円(税込)。なかなかの値段だ。どんな弁当だろう。その日の晩ご飯にしようと思って買い求めた。
2025年5月末に移住した。地方都市は面白い。主に電車と徒歩が移動手段の東京と違って車が主役のまちだから、住まいも店も駅近でなくていい。大きな道路から1本も2本も入った住宅街の真ん中に人気のレストランがあったり、ナビなしでは行きつけないような場所にある店に行列ができたりしている。要は駐車場さえあれば、中心街から多少離れていても問題はないのだ。
スーパーも地元勢が頑張っている。私が愛用しているのは郡山に本社があるヨークベニマル。弁当・総菜類が充実しているし、県産野菜や果物も豊富だ。東京では何軒ものスーパーで様々な弁当を買ったが、弁当類の品数とコスパはヨークベニマルの方が数段上に思える。そしてずらりと並んだ各種弁当を吟味していて気が付いた。「のり弁がある。しかも3種類」
東京のスーパーにのり弁はあったかな? あったような気もするが買ったことはない。ともかくのり弁を食べてみようと思い、3種類とも買い求めた。
まずは「コロッケおかか海苔鮭弁当」(税抜き498円)。のりをめくるとおかかが敷き詰められている。おかずも具沢山で箸が進む。

もうひとつは「塩麹仕込みの焼鮭海苔弁当」(同550円)だ。同じくのりの下にはおかかが控えている。美味い。

珍しいのはイカフライを味噌味に仕立てた「イカカツおかか海苔弁当」(同398円)。

ひとつのスーパーの弁当売り場に3種ののり弁があるというのは、もはや事件と言っていい。

老舗の「郡山島田海苔店」も販売数限定でのり弁を店頭に置いている。ある日、買いに行ったら「予約で完売」だった。そこで翌日電話で予約して店で受け取った。ときどき内容が変わるが、この日の弁当はのりの天ぷらをご飯にのせ、たれをかけたものだった。要するにのりの天丼だ。税込868円。のり専門店らしいアイデアに感心しつつ完食した。

近所の仕出し弁当の店でものり弁を売っている。2200円(税込)の高級弁当で、真ん中に福島牛のすき焼きが盛られ、のりはぎっしり詰まったおかずの下に隠れている。それにしても2000円越えののり弁があろうとは。
お盆の最中、用事があって郡山駅に行った。大きな荷物を持って新幹線から降りて来た人が、次々にあの駅弁の店に行き「海苔のりべん」を買って行く。これから乗る人ではないから、弁当は家で食べるつもりだろう。故郷に帰ったら食べたくなるものをソールフードと呼ぶけれど、郡山の人々にとってのり弁がそうなのではないか。
海苔のりべんは1924年創業の「福豆屋」の看板商品で、駅弁好きや鉄道マニアの間では以前から有名なのだそうだ。のりをめくるまでもなく、隙間からおかかが見える。これでも十分に美味しいのだが、実はご飯の中にもう1枚のりが敷いてあって、その下に昆布の佃煮が隠れている。卵焼き、鮭、えびいも、きんぴらごぼう、かまぼこと、おかずも文句なしの組み合わせ。私はずっと崎陽軒のシウマイ弁当派だったのだが、海苔のりべんを知ってから少し心が揺れてきた。

もともと郡山でのり弁が好まれていたからこの弁当が生まれたのか、それとも福豆屋ののり弁が源流となってのり弁文化が根付いたのか。どちらともわからないけれど、郡山に来たらのり弁をどうぞ。

野瀬泰申(のせやすのぶ)/ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会(愛Bリーグ)会長
1951年福岡県生まれ。食文化研究家。東京都立大卒後、日本経済新聞入社。東京・大阪社会部、大阪文化部長、特別編集委員・特任編集委員を歴任。大阪勤務時代に「ウスターソースで天ぷらを食べる」人々を見て「食の方言」に気づき、取材を続けている。2008年までは日本レコード大賞の審査委員・副審査委員長も務めた。「ご当地グルメでまちおこしの祭典!B-1グランプリ」主催団体「ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会の設立に関与。2018年より現職。著書に「天ぷらにソースをかけますか?」(ちくま文庫)、「食品サンプルの誕生」(同)、「文学ご馳走帖」(幻冬舎新書)など。