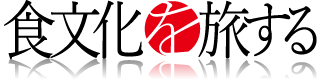埼玉県熊谷市の旧妻沼町には一風変わったご当地いなり寿司がある。茨城県笠間市や京都市伏見区など、いなり寿司がご当地グルメになっている場合は、たいてい稲荷神社のお膝元である場合が多い。稲荷神社には油揚げ、いなり寿司が不可欠だからだ。しかし、妻沼は、高野山真言宗の仏教寺院・聖天山の門前町だ。さらには、西日本は三角形、東日本は俵型が一般的ないなり寿司の形状だが、妻沼のいなり寿司は、まるで春巻きかうまい棒かのような細長い形状をしているのだ。

旧妻沼町は、2005年10月1日に熊谷市および大里郡大里町と合併し、現在では熊谷市の一部となっている。埼玉県北部の県境に位置し、利根川に面することから渡船場として栄えると共に、妻沼聖天山の門前町としても知られる。妻沼聖天山は、日本三大聖天の一つとされ、日光東照宮をほうふつさせる本格的装飾建築で、その精巧さから「埼玉日光」と呼ばれ、国宝に指定されている。水運が主流だった時代にはさぞかし栄えていたであろうことを想像させる町並みだが、現在は中山道(国道17号線)からも、JR高崎線からも離れており、埼玉県民以外には、あまりなじみのない地域と言える。

利根川の水に恵まれた妻沼では、稲作が盛んで、さらに畑にも恵まれ、古くから大豆が栽培されてきた。隣接する行田市も含め、利根川沿岸の地域で豆腐作りが盛んだったことは、行田のご当地グルメ・ゼリーフライの項でも紹介した。そこへ、利根川の水運とともに、江戸で流行したいなり寿司が妻沼へともたらされた。米も油揚げにも事欠かない。となれば、いなり寿司が妻沼の名物になるのは、当然の帰結だ。

シンプルな食材で腹持ちもいい。となれば、河岸で働く人々や、聖天山の参拝者などから歓迎されるようになる。さらに、妻沼聖天山は、大名や豪商が寄進して作られたものではなく、地域の人々の寄付で建立された歴史を持つ。講を作り、聖天山詣での際のハレの食事としても地域に広まった。

稲荷神社のお膝元であることが一般的な、ご当地いなり寿司の中にあって、妻沼のいなり寿司が仏教寺院の門前町で食べられてきた背景は、いくつかの理由があるという。まず、真言宗の加持祈祷などに、霊狐信仰の影響があったこと。また、そもそも「お稲荷様」は、その字を見れば分かるように「稲」との結びつきが強く、農耕神として崇められていたことも考えられる。水に恵まれた水田の多い妻沼に、仏教寺院ながら、稲荷神社と共通した農耕と結びついた信仰があることは不思議ではない。ただ、そうした考え方はたぶん後付けの理由だろう。

そのユニークな細長い形状は、いなり寿司が江戸の食のトレンドとして脚光を浴びた当時そのままの形状なのだそうだ。かつては細長かったいなり寿司が、時代とともに食べやすく小型化していって、今の三角形や俵型になったのだという。江戸と水運で直結していたにもかかわらず、明治以降は主たる交通路から外れたことで、当時の食文化がそのまま残ったのではないだろうか。その証拠に、妻沼のいなり寿司は文化庁が、江戸時代から続く伝統部門として、100年フードに認定している。

しかも、妻沼ではその提供スタイルも独特だ。通常、いなり寿司3本に巻き寿司4個を加え、一人前としている。けっこうな大盛りだ。現在、聖天山の門前でいなり寿司を提供する店は3店舗あるが、そのいずれもが「いなり寿司3本+巻き寿司4個」のスタイルになっている。また、「森川寿司」と「小林寿司」のいなり寿司は3本のうちの1本にかんぴょうが巻かれている。これは、油揚げの破れなどを補強するという「はずれ説」と、ひと味多くしたという「あたり説」の両説があるという。たしかに「森川寿司」のかんぴょう巻きの下には、油揚げが破れて酢飯が見えている。

実際にその3店を訪ね、それぞれのいなり寿司を確認してみよう。聖天山を中心に、3店とも徒歩圏内なので、聖天山にさえたどり着ければ、量はともかく、容易に食べ比べできる。まずは「森川寿司」だ。江戸時代中期、聖天堂建立と同時期に創業した茶屋「毛里川(もりかわ)」が前身という。長い歴史が物語るように、店舗は、本堂のすぐ裏手にある。

「森川寿司」のいなり寿司は、3店の中で最も色が濃い。とはいえ、しょうゆ辛いわけではない。どちらかといえば、甘みが勝っている。3店とも共通しているが、全国各地のいなり寿司には、中の酢飯に野菜など「かやく」が入っていることもあるが、妻沼の場合はシンプルに酢飯のみだ。

次に「小林寿司」。明治時代の門前茶屋がルーツという。かつて、妻沼にも東武熊谷線という鉄道が通じていたが、それは戦中に、兵器工場である利根川対岸の太田の中島飛行機との交通を目指して作られたもの。明治の時代は、やはり水運が最大の交通手段だったのだろう。門前茶屋なので、本堂と利根川のほぼ中間地点に店を構える。

「小林寿司」のいなり寿司は、3店の中では色が最も淡い。とはいえ、薄味というわけではない。しっかり甘みの勝った油揚げで、もっちりとした酢飯を包み込む。盛り方では、唯一いなり寿司の上に巻き寿司がのっていた。

農林水産省のホームページ「うちの郷土料理」の項では妻沼のいなり寿司を「聖天ずし」と本家っぽいネーミングで紹介しているが、実は「聖天寿し」は、戦後の開業と最も歴史が浅い。店は四脚門近くある。

「聖天寿し」のいなり寿司は、3店で唯一かんぴょうが巻かれていなかった。ただ、個人的な感想だが、かんぴょうは「はずれ説」よりも「あたり説」を支持したい。中がシンプルな酢飯のみだけに、かんぴょうの「ひと味」がちょっと嬉しいのだ。

昭和30年代までは、地元の農家は米を重箱に入れて聖天山の門前の店に持参し、聖天ずしと交換していたという。つまりそもそも店で食べるものではなく、持ち帰って食べるのが基本だ。現在でも、3月の桃の節句や5月の端午の節句、春と秋の聖天山の例大祭などの祝い事にはいなり寿司を食べ、彼岸やお盆の来客への手土産としても利用されているという。地域の暮らしに密着した食文化と言えるだろう。