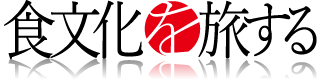おでんや煮物などで人気の食材・こんにゃく。こんにゃく芋が原料であることはよく知られているが、実はこんにゃく芋は非常に重たい上に、腐りやすい。つまり、保存性が悪く、輸送にも適さないということだ。かつて生芋をすりおろして作っていた頃は、産地限定で、しかも生芋が収穫できる秋にしか食べられないものだった。そんなレアな食べものだったこんにゃくがこれだけ普及したのは、こんにゃく芋を薄く切って乾燥させ、さらに細かい粉にしてから作る方法が編み出されたからだ。

発明したのは、江戸時代の1745年に現在の茨城県常陸大宮市で生まれた中島藤右衛門だ。かつて、常陸大宮市や大子町など茨城県北の山間部は、山深く交通の便も悪く、耕作には不向きだったため、水はけの良い砂礫地を好むこんにゃく芋くらいしか農業ができなかった。しかも、こんにゃく芋は成長に数年を要し、冬季は掘り出して温かい室内で保存するなど栽培には非常に手間がかかり、なおかつ重くてすぐ腐るという商品性の低い農産物だった。

その意味で、藤右衛門の発明は画期的で、これによりこんにゃくの販路は北は現在の北海道南からから近畿地方にまで拡がり、水戸藩を代表する産物のひとつに成長した。そこで水戸藩は、粗悪品を排除するために袋田に蒟蒻会所を設置、藤右衛門を頭取に据え、品質の維持を図るようになる。今でこそ、日本で栽培されるこんにゃく芋の約95%が下仁田町を中心とする群馬県産で、製粉加工も群馬県が圧倒的だが、その歴史をひもとくと、実は茨城県常陸大宮市・大子町が、下仁田町に勝るとも劣らない「こんにゃくの聖地」ということになる。

袋田のこんにゃくを堪能するなら、名勝・袋田の滝にも近い「こんにゃく関所」がおすすめだ。もちろん、道の駅やまちなかにある地元産品の直売所「だいご味らんど」でも地元産のこんにゃくを購入できるが、「こんにゃく関所」は工場を併設した直売所でもあり、イートインコーナーもあることから、多種多様な袋田のこんにゃくを選んだり、その場で味わったりすることができる。

店に入ってすぐの場所に陳列されていたのは、秋から春にかけての期間限定商品、生芋こんにゃくだ。藤右衛門の発明以前の製法、生のこんにゃく芋をすりつぶして作ったものだ。昔ながらの製法にこだわり、日持ちさせるための熱殺菌を行なっていない。そのため、賞味期限が短いが、こんにゃく本来の風味、こく、深い味を堪能することができる。とにかく舌触りが良く、スーパーで買う市販のこんにゃくとの違いの大きさに驚かされた。

刺し身用の丹精こんにゃくは、5色のカラフルなこんにゃくだ。白は、こんにゃく粉本来の色味だ。緑は、四万十川の手もみ青のりを加えたもの。黄は、地元産の天然ゆずが加えられている。赤は、やはり地元産のトウガラシが入っている。そしてユニークな黒は、竹炭入りだ。

ユニークなのは、関東最北端の山奥ならではの気候を生かした凍みこんにゃくだ。12月中旬から2月ごろまでの厳冬期、畑にわらを敷き詰めてこんにゃくを並べ、水をかけて、夜間の気温低下で凍らせる。それを昼間の日光でゆっくりと解凍。これを20日ほど繰り返すことで、こんにゃくの水分が抜けスポンジ状になったものだ。元々丹波の製法を袋田に持ち込んで誕生したが、戦後、生産者が激減し、今では、茨城県北部でしか生産されていないという。

イートインコーナーでは、この凍みこんにゃくを天ぷらにして食べさせてくれる。スポンジ状なのだが、けっこうな歯ごたえがある。しっかりとした歯ごたえながらも、どこかこんにゃく特有のくにゅっとした食感もあり、実に美味しい。茨城以外では廃れてしまったというだけに、ぜひとも食べておきたい逸品だ。

定食で、こんにゃくステーキ膳をいただいた。できたてのこんにゃくを熱々のステーキにしてくれる。ショウガとニンニクが効いたタレで、あっさりヘルシーなこんにゃくが、牛肉にも勝るとも劣らないご飯の供となる。ぷるぷるで箸でつかみにくいので、できればナイフとフォークで食べたかった。

藤右衛門の発明を実体験できる手作りこんにゃくセットも販売されている。実際に、こんにゃくを手作りしてみた。パッケージされていたのは、40グラムのこんにゃく粉と3グラムの水酸化カルシウム、それぞれ2袋だ。別途、水1800CCとぬるま湯400CCを用意する。

まず1800CCの水を火にかけ、20~30度に沸かす。そこに40グラムのこんにゃく粉を少しずつ入れ、しゃもじでのり状になるまでよくかき混ぜ、1時間から1時間半そのままにする。40グラムのこんにゃく粉に対し、水が1升と、いかにこんにゃく作りに占める水の割合が大きいかが分かるだろう。

しばらくしていると、水を含んだこんにゃく粉がゼリー状に固まってくる。そうしたら、ボウルにぬるま湯を400CC用意し、そこに水酸化カルシウム3グラムを入れてかき混ぜ、石灰水を作る。ゴム手袋をはめ、ゼリー状になったこんにゃく粉と炭酸水を手早く混ぜる。手で握りしめるようにしっかり混ぜるのがコツだ。

混ぜ終えたらバットなどに入れて形を整えるか、もしくは手や茶碗などで丸く成形する。これを大きめの鍋でたっぷりと沸かしたお湯の中に投入する。20~30分ほど煮れば、アクが抜けるので完成だ。これを水に浸して冷ませば、手作りこんにゃくの完成だ。

今では1年を通じてごく当たり前に、手軽な価格で食べられるこんにゃく。しかし、それは先人の努力があってこそなのだ。袋田を訪ね、その歴史に触れることで、手軽に安くこんにゃくが食べられることのありがたさを、ぜひ肌身に感じてほしい。