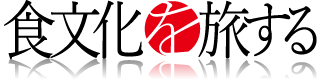そばは、穀物であるソバの実を原料にしたそば粉を麺に加工した、日本特有の麺料理だ。全国各地でざるそばやかけそばが食べられている一方、割子の漆器に入れて食べる出雲そばや、小割りにしたそばを竹で編んだとうじカゴに入れ、軽くゆがき、つゆや具とともにお椀に移し食べる奈川のとうじそばなど、その地域ならではの食べ方もある。東京の春菊天そばも、首都圏以外ではあまり食べない「ご当地そば」の一つと言えるだろう。

ファストフードとしてのそばの歴史は江戸時代にまで遡る。飲食店が営業を終えた深夜帯に、市中の腹を空かした人々にそばを提供していた屋台の「夜鷹そば」がそのルーツだ。このそば屋台は、明暦の大火をきっかけに大流行、江戸後期には3,000軒を超える立ち食いそば店が江戸じゅうに林立したという。屋台という限られた環境で生まれた極力手間を省く調理法は、鉄道が誕生すると「駅そば」へと発展していく。駅そばは信越本線の軽井沢駅で誕生したとされる。難所の碓氷峠を越えるため、機関車の付け替えが必要で、その待ち時間に小腹を空かせた乗客のためにそばを提供したのだという。

江戸の食文化とも言える立ち食いそばに加え、この駅そばも東京を中心とした鉄道駅に広がっていく。名古屋駅ならきしめん、鹿児島本線と長崎本線が分岐する佐賀県の鳥栖駅では、煮込んだ鶏肉が入ったかしわうどんが有名だ。ダイヤによっては、乗り換え時間が限られることもある。おのずと、手間と時間がかからない調理法での提供にならざるを得ない。つまり「早い」ことが、立ち食い・駅そばの真骨頂なのだ。

一部立ち食い店ではそば打ちにこだわる店もあるが、立ち食い・駅そばといえば冷凍麺やゆで麺の温め直しが一般的だ。すでに火が通っているので、温め直してぬめりを取れば、すぐにそばを食べられる。そこに、つゆをかけて食べるのが一般的だ。鴨南蛮やカレー南蛮など煮込み=追加調理が必要なメニューは、当然敬遠される。すぐに食べられる盛りそば、ざるそば、かけそばと言ったメニューが中心になる。トッピングも、わかめや揚げ玉、油揚げ、野菜のかき揚げなど、作り置きしたものをのせるだけというのが一般的だ。

讃岐や北部九州のうどんでもそうであるように、そばなど和の汁麺は天ぷらとの相性がいい。しかし、立ち食い・駅そばの場合、「早さ」だけでなく「安さ」も必要不可欠だ。空いた時間にささっと小腹を満たすことに、多大なコストは掛けられないからだ。となれば、天ぷらも海老や穴子など値の張る魚介ではなく、野菜が中心になる。ニンジンやタマネギに乾燥桜えびを入れたかき揚げが典型的だが、いずれも保存性が高いため、安価で大量に仕入れることができることがその背景にある。

とすれば、葉物の春菊は、手軽な野菜天の中でも「高級」の部類に入る天ぷらネタだろう。普段は春菊天がメニューに載る店でも、季節外れの夏場や、市場が閉まる年末年始明けなどには、春菊天そばのボタンに「売り切れマーク」が点灯するのは、そのためだ。「早い・安い」立ち食い・駅そばの中でも「高級食材」であるならば、その調理法・味にもこだわりたいと言う思いが筆者にはある。

立ち食い・駅そばの天ぷらは、揚げ油の温度を高くしてカリカリに揚げるのが基本だ。揚げ置くので、十分衣の水分を飛ばしておかないと揚げ置くうちに油が回ってグズグズになってしまうからだ。そのまま食べると衣の固さが歯に当たるが、そばつゆに浸せば「戻る」ので問題はない。そして、丸い型枠に入れて揚げるのもまた一般的だ。油の中で形を保つのが難しい食材でも、型枠を使えば職人でなくとも揚げられる。

かりかりのきつね色した丸い春菊天をそばつゆにじっくり浸して食べるのも悪くないが、「早い・安い」の立ち食い・駅そばの中でも「高級食材」である春菊天だけは、より美味しく食べたいとは思わないだろうか。と言うわけで、都内に星の数ほどある春菊天そばの中から、よりおいしいものを見つけることに、実は筆者は血眼になっている。特に春菊天の揚げ方に、その店の立ち食い・駅そばに対するスタンスが表れていると信じて疑わない。そのポイントを①型枠を使わず、春菊本来の姿に揚げる、②揚げ油の油温を上げすぎず適温で揚げる――にあると考えている。

京王線初台駅を出てすぐ、甲州街道沿いにある「加賀」は、10人も入れない、カウンターのみの立ち食い店だ。注目は立ち食いそば店必須のショーケースや揚げ置きの天ぷらを並べるバットがないことだ。そう、立ち食い店にもかかわらず、天ぷらを揚げ置きしないのだ。注文を受けてから天ぷらを揚げる。そして揚げたてをほんの少し油切りをして、そばの上に「じゅっ」とのせる。

もちろん型枠は使わない。春菊の葉そのままを拡げたように揚げる。そのビジュアルは芸術的だ。揚げたてなので、すぐにかじれば、その食感はさくさくだ。決してカリカリではない。それが食べ進むうちに、そばつゆに馴染んでいく。油温が適切なので、衣にはこげ臭さがない。衣がほぐれて「たぬき」になってもなお、立ち食い店とは思えないおいしさを演出する。

初台「加賀」と甲乙つけがたいクオリティーの春菊天そばが食べられるのは、京急大森海岸駅前にある「甲斐そば」だ。こちらも、店頭にショーケースもバットもない。食券を渡すと、そこから調理が始まる。立ち食い店ではなく、店内はすべて椅子席だが、生そばではなく、食券制で春菊天そばが600円と、価格とその調理法の両面で、立ち食い店の範疇に収まる。

春菊天もボリューム満点だ。丼一杯に、初雪をまとった木の葉がごとく、春菊の葉が広がる。油温が適切なので、美しいほど白い。油温が高いと、紅葉の葉になってしまうが、明らかに雪のごとくだ。適温で揚げているので、上面はさくさく、そばつゆに当たった部分はしっとりとした食感になる。夏ならざるで食べるのもいいだろう。

都心では、JR有楽町駅前の「はないち」の春菊天そばが人気だ。やや揚げ油が高めで茶色っぽいのが玉に瑕だが、見事に広がった春菊天のフォルムが美しい。春菊天の量もたっぷりで、都心の春菊天好きにはうれしい店だ。

上野界隈なら、東京メトロ日比谷線仲御徒町駅そばの「匠そば」の春菊天も要注目だ。この店は、もりそばかかけそばを選んで天ぷらは別途注文するシステム。なので、正しくは「かけそば+春菊天」になる。春菊をひと枝、丸々天ぷらに揚げてある。藻塩も添えて、天ぷら単体でも味わえるようになっているところに春菊天に対するリスペクトが感じられる。

JR京葉線潮見駅そばにある「大むら」も要注目だ。同店の最大の魅力は価格の安さだ。かけそば1杯200円。大きな春菊天も1つ100円だ。写真のように春菊天をダブルでのせても400円という驚きの価格になる。揚げ置きのため、高めの油温でカリカリには揚がってはいるものの、見事な春菊の葉のフォルムといいい、なにより400円という価格を考えると非常に魅力的だ。

江戸時代以来の歴史を引き継ぐ東京の立ち食い・駅そばだけに、全店の春菊天そばを食べ比べることはほぼ不可能と言っても過言ではない。星の数ほどある春菊天そばの中から自分の好みの店を探し当てるのもまた、東京の春菊天そばの楽しみ方のひとつの方法だろう。