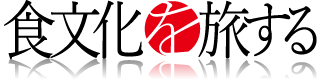豊かな海に恵まれた紀伊半島、南紀の食。前回紹介した串本のかつお茶漬けに続き、今回は新宮のさんま寿司を紹介する。

実は今皆さんが食べている握り寿司、いわゆる江戸前寿司は、かつて「はや寿司」と呼ばれていた。そもそも寿司とは、現在では「なれ寿司」と呼ばれる、魚介類と米、塩を材料として発酵した保存食だ。日持ちのしない鮮魚を、発酵の力を借りて保存できるようにした調理法で、発酵が続く限り、長期にわたって保存できる。琵琶湖沿岸の鮒ずしが有名だ。

一方「はや寿司」は、「なれ寿司」の乳酸発酵で生じる酸味を酢で代替し、酢飯に魚を添えて食べるものだ。発酵を待たずにすぐ食べられることから「はや寿司」と呼ばれた。新宮のさんま寿司は、旧来の「なれ寿司」の一種だ。

さんまは元々冷たい海を好み、東北、オホーツク海、北アメリカなど北太平洋だけに棲息する。秋、北の海で獲れたさんまはたっぷりと脂がのり、蒲焼や塩焼で食べるのが一般的だ。しかし秋の終わりから冬にかけて、さんまは紀州沖へと南下してくる。長旅で程よく脂が抜けたさんまは、お造りやお寿司、干物にして食べるのが一般的だ。

新宮など南紀では、開かずに丸干しで作る干物も多い。紐の両端にさんまをくくりつけて、それを竹竿などに吊して干す。干すことによってうまみを増したさんまは、秋の脂たっぷりの時期とはまた違ったうまさがある。

中には「かんぴんたん」といって、カチカチになるまで長期間干す丸干しもある。水分含有量が少ないので、半年ほど日持ちするのが特徴だ。

なれ寿司のさんま寿司はさらに長期の保存に適する。今回訪れた新宮の「東宝茶屋」では、実に30年物のさんま寿司が食べられる。

まずはさんまを塩漬けし、その後ご飯と一緒に漬け込み、乳酸発酵させる。一般的には数週間発酵させれば食べごろになる。乳酸発酵のため、酸味が加わるのが特徴だ。適度に酸味が加わったその味は、まさに、現在の寿司の原型といえる。横から見ると、粘り気を増し、米粒の形を失いはじめているのがわかる。

乳酸菌の働きで腐敗しないことから長期の保存にも適する。しかし、発酵が進むため、次第にさんまも米も原形をとどめなくなる。「東宝茶屋」の30年物のさんま寿司はもはや液体だ。白い液体は同じ発酵食品のヨーグルトを思い出させる。

味も強い酸味が前面に出てくる。元々がさんまと米だったとは想像がつかないほどの酸っぱさだ。これを、まさに舐めながら日本酒を飲めば、飲みすぎること請け合いだ。

店からは、まださんまと米の形が残る寿司を30年物のなれ寿司に浸して食べることを勧められた。30年の月日を越えた先輩後輩のマリアージュだ。

乳酸発酵の代わりを果たした食酢も、そもそもは日本酒が酸化したもの。いにしえの日本人は、化学変化の力を上手に利用し、おいしいものをよりおいしく、長い時間にわたって食べられるよう工夫をした。そんな自然の持つ力を生かした南紀のごちそうがさんま寿司だ。