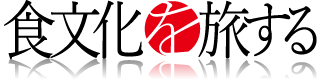2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、日本は工業立国の土台を築き,その後日本の基幹産業となる造船、製鉄・製鋼など石炭と重工業において急速な産業化を遂げた。この世界遺産を構成するものの多くが九州に立地する。九州が、日本近代化の基礎を支えたと言っても過言ではないだろう。

そして、日本近代化のエネルギー源だった石炭を多く産出した北部九州には、そこで働く人々の胃袋を満たした個性的な食文化が存在する。過酷な肉体労働だった炭鉱や高熱と常に向き合う製鉄の現場では、スタミナ満点の食が求められた。そんなくらしから生まれた「ご当地グルメ」が、今も北部九州では愛され続けている。
田川ホルモン鍋

大阪や広島など、額に汗して働く人が多い地域の名物料理にはホルモンを食材にしたものが多い。福井県大野市や岩手県岩泉町などでもご当地ホルモン料理があるが、これはともに鉱山がルーツだ。

過酷な労働だった鉱山には、かつて日本の植民地だった朝鮮半島から多くの人たちが徴用された歴史がある。明治になるまで肉食を忌避していた日本で、各地にホルモン料理が生まれた背景には、徴用された人々のくらしがある。

肉食文化だった朝鮮の人々は、その文化を日本に持ち込む。特にホルモンは、捨てるもの=ほうるもんを語源に持つように正肉に比べて価格が安かったため、炭鉱など多くのエネルギーを必要とするの人々に広がっていく。ホルモン焼きやもつ煮の誕生だ。

そんなホルモン料理の中でも、特に個性的なのが福岡県田川市の田川ホルモン鍋だ。料理名は「鍋」だが、使うのは土鍋ではなく鉄板。中央部分が少し窪んだ鉄板だ。鍋料理にはだしがつきものだが、田川ホルモン鍋はだしは使わない。焼き肉のたれで下味がついたホルモンをタマネギ、キャベツ、モヤシ、ニラなど大量の野菜と一緒に鉄板に盛る。加熱するうちに野菜から出た水分が鉄板の底にたまり、「炒め煮」にして食べる。同じ福岡県でも、だしでもつを煮る博多もつ鍋とは明らかに違う味わいだ。

使われるホルモンはマルチョウ(小腸)、ハチノス(第二胃袋)、ハツ(心臓)。特にたっぷりと内臓脂肪が付いたマルチョウを多く入れる。この脂が炭鉱労働者のスタミナ源になった。炭鉱が閉山した後も、田川の人々は、このホルモン鍋を愛し、田川のご当地グルメとして全国に発信している。

近年では、野菜がたくさん食べられ、コラーゲンなど女性に欠かせない栄養素も多く含まれることから、若い女性にも人気があるという。
大町たろめん

石炭のまちには、個性的な麺料理も誕生した。佐賀県武雄市の武雄・北方ちゃんぽんは、長崎で誕生したちゃんぽんが炭鉱のまちに伝播、海から離れた山中のため、魚介が姿を消し、野菜を中心に、炭鉱労働者の旺盛な食欲を満たすために、山盛りになった。

石炭を使い、鉄を作った戸畑では、丸鶏と鶏ガラ、とんこつで作るちゃんぽんのスープがほぼとんこつになり、揚げ物までのせられ、大幅にカロリーアップする。交替制勤務の製鉄所の短い休憩時間にさっと食べられるよう太いちゃんぽん麺も、すぐに茹で上がる細い蒸し麺に変わる。

同様に、働く人々のくらしぶりを映して誕生したのが、武雄市の隣町、佐賀県大町町の大町たろめんだ。大町町はかつて杵島炭鉱で栄えた地域。
ショウガを効かせた牛骨スープで食べる個性的なうどんだ。具には豚肉やキャベツなどの野菜がたっぷりと入る。牛骨スープと具のボリューム感が、炭鉱労働者の旺盛な食欲を満たした。

実は、大町たろめんは2000年に一時姿を消している。閉山後も町で唯一大町たろめんを提供し続けていた「たろめん食堂」が閉店してしまったのだ。しかし、地元の人たちの大町たろめんへの深い愛情から、有志が立ち上がり、伝統の味を復活させた。

牛骨ならではの味わいとショウガの刺激、そこに中華麺ではなくうどんを入れて食べるのは、ちょっと個性的。実は筑後平野一帯はうどんをよく食べる地域。ラーメンの印象が強いが、腰の弱い独特のうどんが全県で広く食べられている。うどんの大型チェーン店も多い。久留米でもうどん麺を使ったちゃんぽんが誕生しており、牛骨スープのうどんも決して違和感のあるものではない。
方城すいとん

炭鉱労働は命がけ。ガス噴出や落盤など、いつ命を落としても不思議ではない過酷な職業だ。それが故に「宵越しの金は持たない」文化がある。肉体労働者にとって食は命をつなぐ糧でもある。食への投資は惜しまない。炭鉱はなやかなりしころは、経済の中心地・博多よりも質のいい魚が筑豊へ運ばれたという逸話もあるほどだ。
しかし、ひとたび事故が起これば、一度に多くの人が亡くなる。まちのくらしは一変する。そんな悲しい歴史を映しているのが、福岡県福智町の方城すいとんだ。

福智町にかつて存在した三菱方城炭鉱。1914年、開鉱後わずか6年で大災害に見舞われる。「方城大非常」と呼ばれる、日本炭鉱史上最悪のガス爆発事故だ。公式に記録された死者数は671人。日本最悪、世界でも第4位の炭鉱爆発事故だった。実際にはもっと多くの人が亡くなっているという説もある。

この事故の際に、犠牲者の孤児らに振る舞われたのが方城すいとんだった。元々、近所づきあい、相互扶助を大切にしていた炭鉱で暮らす人々は、各家庭から食材を持ち寄り、すいとんを作って食べていた。交代勤務で時間のない炭鉱マンたちにぴったりの「コミュニケーション食」だった。それが、大鍋でさっと作れることから、混乱する被災地の「非常食」にもなった。
鶏肉と季節の野菜がたっぷりと入った汁に、小麦粉を練って作ったすいとんが入る。田川ホルモン鍋や大町たろめんのスタミナ、ボリュームとは対照的な滋味溢れる味わいは、まさに悲しい歴史を物語る。

町内には、犠牲者たちを祭った慰霊碑が建てらている。閉山後、多くの人々がまちを後にし、遺族も少なくなったからだろうか、以前訪れた際には、慰霊碑へと続く道がすっかり草むしていた。日本の近代化は、多くの人々の犠牲の上に成り立っていると言うことを、この方城すいとんとともにかみしめてほしい。
八幡ぎょうざ

筑豊で産出された石炭は、国鉄筑豊本線で若松に運ばれ、海路で各地の工場に出荷されるとともに、対岸の八幡製鉄所で製鉄のエネルギーとして使われた。その八幡にも、長くまちの労働者に愛されてきたご当地グルメがある。八幡ぎょうざだ。
日本近代化の礎になった製鉄業、石炭は国産だったが、鉄鉱石は輸入に頼っていた。海路を通じ、中国との交流が生まれ、ぎょうざが八幡にもやってきたと言われている。

本場中国では水ぎょうざが主流だが、中国東北部には食べ残しのぎょうざを焼いて温め直して食べる文化がある。戦後、旧満州からの引き揚げ者がこの焼きぎょうざを日本に持ち帰り全国各地に根付いてゆく。油を使って焼くためカロリーアップされ、それが身体を使って働く人々に人気を呼んだ。
八幡でぎょうざが人気を呼ぶのもやはり戦後のことだ。大陸からの引き揚げ者を中心に料理屋のメニューに出され、少ない食材でおいしく作れるぎょうざは市民に愛されるようになった。

八幡ぎょうざにはいくつかのバリエーションがある。満州引き揚げ者ではなく、貿易による交流で根付いたと思われる中国本土系は、皮が肉厚であんはジューシー。家庭の味を再現したお母さん系。中国系本土から派生し、水の代わりに、ラーメンなどの豚骨スープを使って焼き上げるラーメン系。そして、八幡ぎょうざの象徴とも言えるのが鉄なべで焼く鉄なべ系だ。

関東などでは鉄なべ餃子というと博多の印象が強いが、実は北九州市八幡西区折尾(現在は黒崎に移転)の「本店鉄なべ」が発祥だ。「本店鉄なべ」創業者が、東京で鉄板にのったスパゲッティを食べた兄の話をヒントに、ぎょうざを熱々のまま食べてもらおうと、京都から平たい日本古来の囲炉鍋を取り寄せて誕生した。これがスタミナを必要とした製鉄所などで働く人々から愛され、定着した。
食はくらしを映す鏡だ。国内はもちろん広く世界には様々な気候、風土のまちがある。日本のような島国では魚貝を好んで食べるが、大陸の奥では肉が主なたんぱく源だ。気候風土が違えばできる野菜も違う。寒さが厳しく冬は新鮮な野菜が手に入らない内陸地域では、野菜を塩漬けにしたり、乳酸発酵させたりして保存するなど、その土地ならではの食べ方が発達する。炭鉱労働など、その土地の人々の暮らしぶりもまた料理に影響する。
食べている料理がどういう経緯で、どのように誕生したかを調べてみると、よりいっそうおいしく感じられるはずだ。