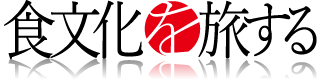郡山に住まいを移して知ったのだが、この街は公園都市と呼ぶのがふさわしい。街の中心でもある市役所の前に広がるのが野球場や陸上競技場、室内プール、弓道場などを備えた広さ30ヘクタールの開成山公園で、夏休みや週末になると声援や音楽が響き渡る。
スポーツ関連施設を過ぎるとバラ園、「五十鈴湖」という名の池、野外音楽堂、遊具などを配した園地になる。カフェで談笑する人々もいれば、ベーカリーでパンを買う人、ペットショップを覗く人もいて、贅沢な時間が流れている。全体が芝生と樹木で覆われているので、いつ行っても散歩中の犬に出合う。

そしてここは桜の名所として知られている。引っ越してきたとき、桜のシーズンは終わっていたから、来年の春がいまから楽しみだ。
公園と道を挟んだところに立つ開成山大神宮は「東北のお伊勢さま」と呼ばれていて、正月の三が日、初詣の人々が途絶えることなく訪れる。
そこから東に徒歩20分弱。21世紀記念公園と麓山(はやま)公園がある。前者は近代的な公園だが、後者は1824年に造られた歴史ある公園で、池や滝を備えている。道を隔てて続いているので、両方の公園を歩いてみれば、江戸時代と現代をまたいで散歩ができる。

市内には大小300もの公園があると市のHPに書いてあるけれど、なるほど車を走らせればあちこちで公園にぶつかる。その中にひとつ気になる公園があったので出かけてみた。市の西部、町場が途切れて人家が少なくなる逢瀬地区にある逢瀬公園だ。ここは県営で高低差のある敷地は広大。1枚の写真に収まる規模ではない。
目当ては公園そのものではなく、駐車場のそばで営む「おうせ茶屋」だった。麺類、おにぎり、甘味までメニューは豊富。訪れたのは平日の午後だったが、客が次々にやってくる。その場で注文したものを食べる人に混じって、リピーターらしい人が持ち帰りする姿も見られる。

私が買ったのは逢瀬地区とその周辺の家庭料理「キャベツ餅」だ。ざく切りにしたキャベツを炒め、しんなりしたら醤油、みりん、酒、だしなど加えて味付けし、餅に絡めて出来上がり。茶屋ではパックに入れて売っていて、餅2個で360円と手ごろだ。
店の前のテーブル席で食べてみた。初めてのことだったから、キャベツと餅がどう絡み合うのか想像できなかった。キャベツと餅を一緒に箸でつまんで口に入れる。「おおー」と小さな声が出た。実に美味い。キャベツと餅の歯触りのわずかな差が、いい塩梅なのだ。味は日本人定番の醤油ベースなので、組み合わせの意外さが気にならない。それどころか目から鱗のコンビネーションだ。

いつごろ誰が最初にこしらえたのか定かではないというが、地域ではいまでも人気の一品として食べ継がれている。茶屋の女性に尋ねたら「昔は玉菜餅と呼んだんです。菜っ葉餅もあって、これはキャベツの代わりに白菜ね」。「玉菜」というのはキャベツの古い呼び名だ。
周辺には農家が多いから余った野菜と手元の餅を併せた料理が生まれたのだろう。
話を戻せば、郡山には池を囲む公園がいくつもある。明治の初めに安積疎水の開削によって猪苗代湖の水が引かれるまで、灌漑用のため池に頼っていた。疎水の完成でため池の役割は終わり、ある池は公園に姿を変え、ある池は鯉の養殖場になった。その結果、郡山市は市町村別の鯉の生産量が全国1位に。いまは「鯉を食べようと」呼びかける「鯉に恋する郡山プロジェクト」が大々的に繰り広げられている。

野瀬泰申(のせやすのぶ)/ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会(愛Bリーグ)会長
1951年福岡県生まれ。食文化研究家。東京都立大卒後、日本経済新聞入社。東京・大阪社会部、大阪文化部長、特別編集委員・特任編集委員を歴任。大阪勤務時代に「ウスターソースで天ぷらを食べる」人々を見て「食の方言」に気づき、取材を続けている。2008年までは日本レコード大賞の審査委員・副審査委員長も務めた。「ご当地グルメでまちおこしの祭典!B-1グランプリ」主催団体「ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会の設立に関与。2018年より現職。著書に「天ぷらにソースをかけますか?」(ちくま文庫)、「食品サンプルの誕生」(同)、「文学ご馳走帖」(幻冬舎新書)など。