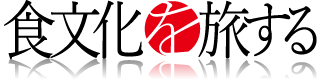東京多摩地区から埼玉県北部を経て群馬県に至るまでは、広く麦が食べられている地域だ。麦食の代表格といえるのがうどんで、武蔵野うどん、加須うどん、館林うどんなど、各地に名物うどんがある。そんな関東のうどんの中でも、もっとも知名度が高いのが、群馬県の水沢うどんではないだろうか。

水沢うどんは、秋田県の稲庭うどん、香川県の讃岐うどんと並び「日本三大うどん」のひとつに数えられる。水沢うどんは、約1300年前の飛鳥時代に開基され五徳山水澤寺(水澤観世音)の参道で誕生した。水澤寺創建に尽力した高麗からの渡来僧が伝えた製法がそのルーツと言われる。天正4(1576)年ころからは、参拝者や伊香保温泉の湯治客に、地元産の小麦と水沢の湧水で打ったうどんを供するようになった。現在では、水澤寺の参道に10軒を超えるうどん屋が、まさに軒を連ねている。

麺は、古来の伝統を守り、小麦粉、塩と水沢の清水だけで、でんぷんなどの添加物は一切使わずに打つ。打った麺は軽く干してからゆでたのが始まりとされるが、現在では生麺や土産用には乾麺もある。ゆであがった麺は、冷たくシメで、つけ汁に浸して食べる。やや細めで、コシと弾力があり、白く透き通ってつるつるとした食感が特徴だ。つゆは、ごまとしょうゆの2種類で食べる店が多い。

実際にお店で水沢うどんを食べてみよう。看板に「始祖」を掲げるのは「清水屋」だ。店内には明治末期のころの写真が掲げられ「当時の水澤では当店舗のみがうどんの提供を致しておりました」と記されている。1886(明治19)年に有栖川宮熾仁親王の来店を皮切りに、昭和天皇はじめ多くの皇族が水沢うどんを召し上がったという由緒ある老舗だ。

農林61号など地元・群馬県産の無農薬小麦をはじめ、国産小麦粉を中心に独自にブレンドして使い、手打ちにこだわる。小麦粉を混ぜる際の感覚、こねる動作、こねた後の足踏み、寝かせた後の再度の足踏み、のばす、切る――伝統の技を極めた職人の手打ちで、厳選した素材を水沢うどんに仕上げる。ちなみに、同店では、うどんを中国伝来の「饂飩=うむどん」と呼称する。

ごまとしょうゆの2種類のたれで知られる水沢うどんだが、「清水屋」では、ごまだれがデフォルトだ。しょうゆだれは別注文になる。ごまだれの材料は、白ごまとだし、そしてかえし。化学調味料は使わない。ショウガのしぼり汁を入れることで、コクとキレを生み出し、うどんの味を邪魔しないたれを実現したという。

話し好きのご主人は、ぜひざるを食べてほしいと勧める。うどんは、デフォルトの麺に加え、群馬県産有機栽培の農林61号を使った地粉うどんも用意する。食べ比べしたければ、2種類のうどんを合わせ盛りにした相盛りもある。味を確認すべく、ごまだれに加え、しょうゆだれも追加した。さらに、薬味として山椒オイルと自家製焼き味噌も追加した。

麺の上にのった切れ端が手打ちの証左だ。花や木の葉の形に型で抜いてあるのも、ちょっとした「ひと手間」だ。まずは、デフォルトであるごまだれに浸してうどんをすする。「清水屋」では昔ながらの干し麺にこだわる。生麺ではなく、かといって乾麺でもない。軽く干すのだそうだ。その歯ごたえにまず驚かされた。明らかに芯を感じられる食感だ。地粉うどんも同様だった。いずれも豊かな小麦の風味が味わえる。

ごまだれは、ごまらしいコクの深さが印象的だ。あっさり、細めのうどんに、しっかりと味を添えてくれる。とはいえ、決してうどんそのものの味を打ち消すような強さではない。坂道を上ってきた参拝客には、うどんの炭水化物と、このごまだれの「油分」が、疲労回復につながったのではないだろうか。

別注のしょうゆだれもやや味が強めだ。とはいえ、胡麻だれ同様、うどんの味を打ち消さないギリギリの味付けといえる。かつおぶしのだし感としょうゆの味もしっかりと伝わってくる。

けっこうお気に入りだったのが、山椒オイルだ。ごま以上にスレートに「油」なのだが、これがあっさりシンプルなうどんによく合うのだ。水沢うどん本来の持ち味を味わうには、ちょっと反則技かもしれないが、山椒の強い刺激も加わって、非常にくせになる味だ。焼き味噌は、直接うどんにつけてもいいし、胡麻だれに加えて味わうのも一興とか。

食べ比べのため、隣接する「元祖」を看板に掲げる「田丸屋」も訪れた。食堂風の「清水屋」に対し、「田丸屋」は料亭の装いだ。奥には大きな広間もある。テーブル席も靴を脱いで上がるシステムだ。同店では、水沢うどんのデフォルトとも言える2色つゆのもりうどんと地粉で作った古伝喜利麦をいただいた。

白い十割のもりうどんは、厳選した国産の小麦をのみを使用。水沢の水と天然塩を使い、熟成させながら麺に打つ。「一番干し」と呼ばれる、軽く干した麺もあり、土産用には用意するものの、店内で提供するのは生麺だそうだ。ちなみに、土産用には乾麺もある。「清水屋」のしっかりしたコシに対し、ソフトなコシが特徴だ。よりコシの強い麺が好きな人は「清水屋」、適度なコシが好みなら「田丸屋」だろう。

つゆも、うどん同様にややソフトな味わいだ。熟成した本枯れのかつおぶしとまぐろぶしを使い、濃厚ながらも雑味の少ない味を実現しているという。しっかりとだしの味を効かせつつ、うどんの味わいを引き立たせるかのような味わいだ。

一方、古伝喜利麦は、うどん作りの原点に戻り、国産小麦十割を自家製粉した、全粒粉で打っているとのこと。昔のうどんは茶色かった。そんなうどんを食べてもらいたいとの思いで誕生したという。食べ方は、温かいうどんを、塩、あるいはオリーブオイルをつけて。全粒粉なので、香ばしい風味と歯ごたえのある食感が特徴だ。試しに、もりうどんのつゆでも食べてみたが、味が強いので、よりはっきりしているオリーブオイルや塩の方が確かに食べやすかった。

ちなみに、水沢うどんのお供として知られる舞茸天は「大澤屋」発祥と「清水屋」のご主人が教えてくれた。各店それぞれに特色があるようだ。参道の「水沢うどん街道」以外にも、近隣に水沢うどんを提供する店は多い。伊香保温泉への道すがら、水沢うどんの食べ比べというのも一興だろう。