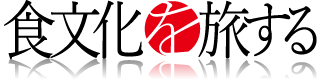総務省統計局が発表する家計調査(2022~24年平均)によると、全国の県庁所在地および政令指定都市の中で、横浜市の2人以上の世帯が年間にしゅうまいに支出する金額は2,612円で、全国平均の1,139円の倍を超えている。さらに第2位の川崎市の1,671円も大幅に上回る。横浜市民は、とにかくしゅうまいをよく食べるのだ。

その背景に、横浜を代表する観光スポットである中華街の存在が大きいことは否めないが、それ以上に横浜=しゅうまいのイメージを定着させたのには「崎陽軒」の果たした役割が非常に大きいと言われている。なぜなら、「崎陽軒」は新たな横浜名物を創造すべく、独自のしゅうまい作りに取り組み、それを果たしたからだ。

「崎陽軒」は、1908(明治41)年に、横浜駅(現在の桜木町駅)構内営業の許可を受け、牛乳やサイダーなどの飲み物、餅、寿司などの販売からスタートした。1915(大正4)年に横浜駅が今の場所に移転するとともに、駅弁の販売に着手。しかし横浜駅は東京駅まで行くには、弁当を食べるには短すぎ、東京駅から乗ってもまだ乗ったばかりという環境で、駅弁の販売はあまり芳しくなかった。

その後、1923(大正12)年の関東大震災で、横浜のまちと「崎陽軒」は壊滅的な被害を受ける。「崎陽軒」の野並茂吉社長は、復興ために、弁当以外に横浜ならではの名物をつくり出そうと、中華街でよく食べられたいたしゅうまいに目をつける。蒸したてで売ることができない駅でも、冷めても美味しく食べらるよう工夫して誕生したのが「崎陽軒」のシウマイだ。つまり、「崎陽軒」のシウマイは横浜名物になるべくして編み出され、見事に横浜名物になりえたという訳だ。

そうした「崎陽軒」のシウマイの歴史とその美味しさの魅力は、同社横浜工場で間近に見ることができる。同工場では、見学プログラムが用意されており、事前予約の上、工場内部を見学できる。しかし、非常に人気のプログラムで、予約は先々までいっぱいだ。ただ、工場入り口にはプチミュージアムショップがあり、ごくごく簡単だが、予約なしでも、その歴史と魅力の一端には触れることができる。

「崎陽軒」のシウマイの原材料は、豚肉、タマネギ、北海道オホーツク産の干しホタテ貝柱、グリーンピース、塩、コショウ、でんぷん、そして皮の小麦粉のみというシンプルさだ。冷めても美味しいその秘訣は、干しホタテ貝柱にある。工場内にも展示されていた干しホタテ貝柱を大量に入れることで、冷めても風味を損なわない工夫がされている。

ちなみに、グリーンピースの役割は彩りのためではない。丸いグリーンピースを入れることで、具材を混ぜ合わせる際、食材同士がより動き、混ざりやすくなるのだとか。そのため、よくあるしゅうまいの上に一粒グリーンピースが乗るのではなく、「崎陽軒」の場合は、あんの中にグリーンピースが入っている。

具材を混ぜ合わせて皮で包み、加熱して包装するまでのラインがガラス越しに見学できる。見学できるのは、シウマイ作りだけではない。「崎陽軒」のもうひとつの看板商品である弁当作りの製造ラインも間近に見ることができる。ずらりと一直線に並んだスタッフがご飯も含め10種類の食材を手早く、整然と経木の弁当箱に詰め込んでいく。

当初弁当のシウマイは4個だったそうだが、現在は5個となり、そのほかのおかずも変遷を経ながら現在のバリエーションになった。その中でも特に人気が高いのが筍煮だ。シウマイに次ぐ人気という。甘辛く、しっかりと煮込まれたその味付けは、ご飯はもちろん、酒のつまみにも相性がいい。

見学の最後は、お楽しみの試食だ。試食できるのは、昭和の発売以来、変わらないレシピで作り続けられてきた昔ながらのシウマイと粗挽きの干しホタテ貝柱と豚肉の旨みを詰め込んだ、大粒で濃厚・ジューシーな特製シウマイだ。人気おかずの筍煮も試食できる。特に、昔ながらのシウマイと特製シウマイを食べ比べできるのはうれしい。通常は、いずれも6個入りからの販売なので、ひとりで12個買わなくても食べ比べられるのはうれしい。

「崎陽軒」の工場見学の魅力は、その製造過程を間近で見たり、できたてのホカホカのシウマイを食べられるだけではない。ひょうちゃんの歴史やその魅力についても、過去の数多くのひょうちゃんを見比べながら、その変遷や秘められたストーリーの数々を聞くことができる。

「ひょうちゃん」とは、シウマイの箱に入った磁器製のしょう油入れのこと。笑った顔、怒った顔…その表情は様々なバリエーションがあり、シウマイに勝るとも劣らない横浜名物になっている。驚かされたのは、初代のひょうちゃんには、顔がなかったということ。1955年に、「フクちゃん」で知られる漫画家の横山隆一さんが「目鼻をつけてあげよう」とたくさんの表情を描いたのをきっかけに、表情豊かになっていく。

いろは48文字にちなんで48種類で誕生。横山さん自ら「ひょうちゃん」と名付けたという。ちなみに試食用のシウマイは、昔ながらと特製の2個だが、特別にひょうちゃんが付いてくる。食べ終えた後は、ビニール袋に入れたひょうちゃんを持ち帰ることができる。

横浜市内では、JRや京急のエキナカに必ずと言っていいほど「崎陽軒」の売店を見かける。市民のくらしの中にしっかりと根を張っていることが肌で感じられる。首都圏に住んでいると当たり前のように感じる「崎陽軒」のシウマイだが、実は神奈川・東京・千葉・埼玉の首都圏4県と静岡圏に商圏は限られている。この味が日々当たり前のように食べられることは、地元民ならではの特権なのだ。ありがたくいただきたい。