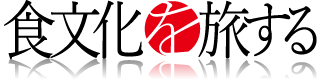中華料理の人気メニューのひとつ、タンタンメン。以前にも紹介したが、本場・中国四川省で誕生した本来のタンタンメンは、汁なしが一般的で、豆板醤や芝麻醤を効かせたものは、実は日本で誕生した和風創作中華料理だ。それもあってか、ラー油をたっぷり使った千葉・勝浦のタンタンメンやあんかけスタイルの小田原タンタンメンなど、地元流にアレンジされたものも見かけられる。そんな「ご当地タンタンメン」のひとつが、溶き卵を使った川崎タンタンメンだ。

実は川崎タンタンメン。その歴史的背景がよく分からない。しかし、川崎・鶴見周辺の主として臨海の工業地帯にある町中華で提供されていることが多い。内陸部の住宅街や、本格中華の店では見かけないのだ。卵とじのタンタンメンとして全国的に知られているのは、チェーン店の「ニュータンタンメン本舗」だ。創業は1964年で、川崎市を中心に40を超える店舗を展開している。

創業者がスタミナがつく料理として独自に創作したことから、ニュータンタンメンと名付けられたという。鶏ガラでだしをとったスープに粗挽きのトウガラシ、溶き卵、ニンニク、ひき肉が主たる構成要素だ。粗挽きのトウガラシを使うため、パンチの効いた辛みが特徴だ。しかし、溶き卵を入れ、ニンニクの風味を加えることで、辛み一辺倒ではない独特の美味しさを醸し出す。

トウガラシの量を増やしたり減らしたりすることで、好みの辛さに調整することも可能だ。粗挽きのトウガラシは、粉末と違い、麺に絡みつくのが特徴だ。また、熱が加わった溶き卵の中でも存在感を発揮する。マイルドな中にもしっかりと辛さを主張しているのが、「ニュータンタンメン本舗」のニュータンタンメンだ。

しかし、川崎・鶴見近辺の町中華で食べられる溶き卵入りの川崎タンタンメンは、ニュータンタンメンとも微妙に味わいが違う。しかも、提供店は、歴史を持つ老舗店ばかり。京急川崎駅そばに店舗を構える「天龍」は、戦後すぐの創業だ。週末ともなると、1日じゅう空き席待ちの行列でごった返す人気店。同店のタンタンメンも溶き卵が入る。しかし、ニュータンタンメンとは微妙に違うのだ。

まずは、うっすらと胡麻が香るのだ。かといって、一般的な芝麻醤を使ったタンタンメンとも明確に違う味だ。具にはニラやネギが入っていて、挽肉をメインにした一般的なタンタンメンとは明らかに違う。そして溶き卵のたっぷりと入ったスープに辛味を加えているのは、ニュータンタンメンの粗挽きトウガラシとは違い、粉末のトウガラシだ。しかも、辛さがかなりマイルドになっている。スープの色も、ニュータンタンメンの真っ赤に対し、ほぼオレンジ色といった具合いだ。

そもそも川崎では古くから溶き卵の入ったタンタンメンが食べられていたのか、それともニュータンタンメンのチェーン展開を受けてそれを取り入れたのか、今のところ定かではない。とはいえ、「ニュータンタンメン本舗」以外の店でも、けっこう溶き卵入りのタンタンメンが提供されていることは間違いない。

少し内陸に入った、南武線矢向駅の近くにある「金華園」では、玉子タンタンメンとニラタンタンメンの2種類のタンタンメンが提供されている。住宅街ではあるものの、歴史を感じさせる店構えだ。一見、「天龍」で食べたタンタンメンを2分割したような、色合い、具の構成になっている。

いずれもトウガラシは粉末だった。玉子タンタンメンは、挽肉にたっぷりの溶き卵が入っている。トウガラシが粉末なので、麺を引き上げても、そこにトウガラシは絡んでこない。それもあるが、全体的に辛みはマイルドだ。たっぷりの溶き卵が、ほんのり甘さを感じさせる。

一方で、ニラタンタンメンはニラがたっぷりと入っている。クセの強いニラの香りが、丼全体を支配している感覚だ。辛みは控えめだが、溶き卵がない分、玉子タンタンメンよりは辛みを感じやすい。いずれにせよ、辛みを抑えめにしている分、スープのうまみが引き立っている。

さらに京急鶴見駅近くにある「ラーメンいろは」も訪れた。歴史を感じさせる店構えだが、訪れた日、客の多くは労務者風で、昼前から呑んでいる客も複数いた。現場で汗して働く人たちに愛されているのだろう。同店のタンタンメンはニラをたっぷりの溶き卵でとじたものだった。まさに「金華園」の2種類のタンタンメンを合体させたかのよう。しかも、辛みよりもごま油の香りが立っている。一般のタンタンメンの芝麻醤や「天龍」の胡麻とも違う、明確にごま油の香りと味だ。ちなみに同店から歩いて30秒ほどの場所にあった中華料理屋のタンタンメンは芝麻醤入りの一般的なものだった。

念のため、内陸の宮前区、宮崎台駅前にある「北京」を訪ねると、名物のタンタンメンは小田原タイプのあんかけだった。チェーン展開している「ニュータンタンメン本舗」は別として、やはり町中華の卵とじタンタンメンは、沿岸部、工業地帯で主に食べられているという調査結果になった。

1点気になるのは、溶き卵タンタンメン地帯にあるセメント通りのコリアンタウンの存在だ。戦中から旧浅野セメントの労働力として同地に定着した韓国・朝鮮にルーツを持つ人々が営んだ焼き肉店が多く軒を連ねる。溶き卵には、そこのカルビクッパの影響があるのではないかとも推察できる。ただし、どうにも確証がない。ちなみに、セメント通りにもほど近い場所にある居酒屋「tenkoh」で、シメのタンタンメンを食べてみた。やはり胡椒辛さの効いた溶き卵入りのタンタンメンだった。

歴史や背景が今ひとつはっきりしないのがどうにも気になるが、一つ言えることは、川崎から鶴見にかけての臨海部では、デフォルトのタンタンメンは溶き卵入りである、ということだ。「ニュータンタンメン」チェーンのメニューというのではなく、地域を代表する「ご当地グルメ」であろう、ということだ。