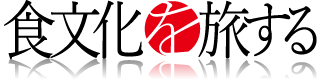今年9月で、甲府鳥もつ煮でみなさまの縁をとりもつ隊がB-1グランプリ厚木大会でゴールドグランプリを受賞して10周年を迎えた。当時、受賞の報が流れた直後から、都心から車で2時間ほどの甲府には、鳥もつ煮を求めて多くの人々が殺到。戦後に誕生し、地元民に愛され続けたご当地グルメは一夜にして全国ブランドとなった。

甲府鳥もつ煮は、新鮮な鳥のレバー、ハツ、砂肝、玉道(キンカン~生まれる前の卵)を鍋に入れ、砂糖としょうゆだけで味付けする甲府ならではのもつ煮だ。うなぎの蒲焼のタレにも似た甘辛い味が、ご飯のおかずにも酒の肴にもぴったりと合う。
もつ煮というと、大鍋でじっくりと煮込む調理法が一般的だが、甲府鳥もつ煮は、手鍋を使って炒り煮にするが特徴で、その背景には、そば店で生まれたという経緯がある。

その誕生は、戦後の1950年頃にさかのぼる。地元で肉卸を営む「鳥林」の3代目店主・荻野明氏が、鳥もつを何とか有効活用できないものかと、取引先である甲府駅前の人気店「奥藤本店」の2代目店主・塩見勇造氏に相談をもちかけたのがきっかけだ。当時は、内臓を食べる文化がなく、鳥もつは捨てられていたという。
勇造氏は、そば店の酒肴品、炒り鳥の調理法を鳥もつに応用できないかと思いつく。炒り鳥とは、鍋に砂糖としょうゆを煮立て、そこに薄く切った鶏肉を入れて炒り煮にする、そば店の限られた厨房でも調理可能なシンプルな料理だ。

ところが、当初はなかなか満足のいくできばえにならなかったという。店の正式なメニューになるまでに何度も試行錯誤が繰り返された。
当時の奥藤本店は、そばを中心にした「奥藤本店本館」と、とんかつやカレーライスなど幅広く庶民向けの食事を提供していた「奥とお別館」が軒を連ねていた。甲府鳥もつ煮の調理法を完成させたのは、「奥とお別館」の調理を任されていた塩見力造氏だ。

まずは、たっぷりの砂糖としょうゆでじっくりと鳥もつを煮込む。そして最後にたれを捨て、強火で鍋をふりながら炒めてもつにてりを加える。しっかりと味の染みた、それでいて目にも美しいてりを兼ね備えた甲府鳥もつ煮が力造氏の手によって完成する。

しかし、昭和30年前後の甲府では、やはりもつを食べることへの敷居は高かった。毎日のように、売れ残りの鳥もつを自分たちで食べる日々が続く。それでもあきらめずに提供し続けるうち、次第に甲府市民にも鳥もつ煮が受け入れられるようになる。
その大きな原動力になったのが、昭和の政界のドンと呼ばれた地元選出の国会議員・金丸信氏だ。金丸氏は、多くの客を伴って奥藤本店を訪れ、鳥もつ煮を食べさせた。

昭和40年代に入ると、鳥もつ丼が人気を呼ぶ。甘辛で味の濃い鳥もつ煮はご飯によく合う味付けで、しかも安価。当時の甲府駅周辺は、公務員らでたいへんなにぎわいだったという。そうした人々に、安くてお腹いっぱいになる鳥もつ丼が愛された。
大鍋で煮る煮込みと違い、1食ずつ炒り煮にする甲府鳥もつ煮は調理に手間がかかる。注文が入ってから調理を始め、完成までに約15分を要する。限られた食事の時間に、1人でも多くの人に鳥もつ煮を提供するためには、生の鳥もつを手早く、しかしじっくりと調理する技量が求められる。特に、鍋をふりながらてりを出す仕上げの作業は職人技だ。力造氏らがその腕を競うことで、奥藤本店からは、多くの鳥もつ煮名人が誕生する。

昭和40年代央には、新聞紙上で「天空の魔味」と紹介され、すっかり定着。鳥もつ煮は甲府市民のソウルフードになった。
やがて、高度成長期を経てくらしが豊かになっていくと、鳥もつ丼の人気が下火になっていく。丼よりも定食で鳥もつ煮を食べるようになり、さらには酒のつまみとしての注文が増えていく。そして、鳥もつ丼はメニューから消える。
現在は、ランチならそばとのセット、夜は酒のつまみが定番だ。

2008年6月には「鳥もつ煮で甲府を元気に!」を合言葉に、甲府市職員有志によるボランティア団体、甲府鳥もつ煮でみなさまの縁をとりもつ隊が結成。2010年のB-1グランプリ厚木大会に出展、初出展で最高位のゴールドグランプリを受賞した。
ゴールドグランプリ受賞直後は、鳥もつ煮を求める人が甲府に殺到。それまでメニューになかった店まで、見よう見まねで調理、提供するような時期もあった。しかし10年の時を経て淘汰が進み、今では奥藤本店や奥藤ののれんを掲げる各店をはじめ、しっかりと調理技法を体得した職人が腕をふるう鳥もつ煮が、市内の多くの店で味わえる。

一時期のティラミスなど、皆がこぞって食べていた人気メニューがブームの終焉とともにあまり食べられなくなった例は多い。あんなに人気の高かったタピオカもそろそろ飽きられてきているようだ。しかし、人々の暮らしとともに、しっかりと地元に根を下ろしたご当地グルメ、ソウルフードは、全国的なブームには関係なく、地元で食べ続けられている。
戦後70年、甲府市民のくらしとともに歩み続けてきた甲府鳥もつ煮のてり、輝きは、今後も決して色あせることはないだろう。