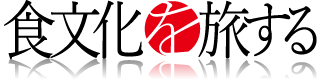長野県小布施町は、県の北東に位置し、県内では最も面積の小さい自治体だ。一方で、葛飾北斎をはじめ歴史的遺産を生かした町づくりに取り組んでおり、北信濃地域有数の観光地として知られる。そんな小布施の秋の観光の目玉が栗だ。江戸時代から栗の産地として名が知られている。町域が狭いことから、その生産量は決して多くはないが、収穫率と品質が高いことから、全国的なブランドとして有名だ。

小布施は、江戸時代初期に松代藩の御林となり、収穫した栗を厳選、将軍家に献上していたという歴史を持つ。水はけの良い扇状地で、酸性の土壌もあり、北信濃の気候も栗の生産に適していた。その美味しさから、江戸時代から、京都の丹波栗とともに知られ、江戸時代以来のブランド栗となっている。そんな小布施に栗のシーズンがやってくると、まちの中心地はたいへんなにぎわいになる。小布施文化観光協会では、9月に入ると毎年、協会主催で栗拾いを開催する。

江戸時代以来という長い歴史は、小布施に老舗栗菓子店を生み出した。単においしい栗を生産するというだけでなく、小布施を訪れれば、そこで歴史に裏打ちされた栗菓子が味わえることが、小布施の栗の名を高めている。小布施の「栗菓子御三家」と呼ばれる3店のうち、「桜井甘精堂」は1808(文化5)年の創業、残る「竹風堂」と「小布施堂」も明治中期から後期に掛けての創業だ。

この時期、特に栗好きの注目を集めるのが、「小布施堂」の栗の点心、朱雀だ。採れたての新栗を蒸して裏ごししたものを、砂糖も何も加えずに、そのまま栗あんの上に盛った、優美な和菓子だ。栗の繊細な風味を損なわないよう、注文を受けてから調理するのだという。提供期間は、毎年新栗が届く1カ月間、今年は9月10日から10月16日までだ。

作り置きができないことから、提供数も限られる。予約も可能だが、9月末現在で、最終日までの予約はすべて埋まっている。それほどの人気なのだ。ただし、毎日12時15分から提供される24席分は予約なしの当日券となる。この当日券を求めて、連日、早い時間から行列ができる。

整理券の配布は、今年は提供時間の1時間前、11時15分からだ。訪れた日は、9時過ぎに到着したが、すでに数名が行列済みだった。もちろん、整理券配布時間のはるか前に24席分は埋まってしまった。そこから2時間と少し行列した後、整理券を確保。提供開始時間までまちなかを散策する。

どこもかしこも行列だらけだ。栗の最もシンプルな味わい方であろう焼き栗も、小布施中心街の数カ所で販売されているが、焼き栗機の前には長い行列ができていた。焼き栗機を数台並べて作業するものの、高圧で栗を蒸し焼きにするため、調理には時間が掛かる。焼き上がった栗はすぐに売れてしまい、次の焼き上がりを待つことになる。

しばらく散策して「小布施堂」に戻る。いよいよ朱雀のおでましだ。漆器の上にのせられた朱雀は確かに繊細だ。新栗を蒸して裏ごししたものは、押し出しだろう、非常に細い麺状になっている。和風のモンブランだ。しかし、甘みは加えられていない。栗そのものが持つ甘みだけだ。

蒸し栗を裏ごししてあるだけにその舌触りは繊細だ。箸でつまむとほろほろと崩れてしまう。まずは、そのふわふわの食感を楽しむ。水分も加えていないので、しっとりとしつつも栗らしいほくほく感も残る。通常の栗菓子やモンブランでは味わえない、なんとも言えない舌触りだ。

この微妙な湿度が、口の中いっぱいに栗の味を拡げる。時折、添えられたお茶をすすらないと咽せてしまうのではないかと思うくらいの微妙な湿度感だ。そしてしばらく食べ進むと栗あんに到達する。ここで初めて加えられた甘みを感じる。とはいえ、優しい甘みだ。確かに、過酷な争奪戦が理解できるだけの、他では味わえない栗菓子だ。

江戸時代創業の「桜井甘精堂カフェ茶蔵」では、洋菓子のモンブランを食べてみた。絞り出した栗のペーストは、自然な栗の色合いだ。「桜井甘精堂」の栗菓子のモットーは、「少しくらい不恰好でもいい」。栗は変色しやすい果実。漂白をして着色すればきれいな色合いも出せるが、それでは栗本来の風味が損なわれるため、添加物を一切使用していないという。

栗のペーストの下の生クリーム、カスタードクリームとスポンジがいかにも洋菓子だ。朱雀でも感じたが、栗のほくほく感は、菓子にする際、やや水分が不足がちになる。それを生クリームがバランス良くカバーしている。さらにスポンジも加えることによってボリューム感も出てくる。ブランド栗、小布施の栗だからとじっくり味わうことで、モンブランの魅力を再発見できた気がする。

「竹風堂」では、栗をたっぷり混ぜこんで、ふっくら炊き上げた栗おこわをいただく。ひとくち食べて感じたのは、甘くないこと。栗そのものが持つ自然な甘さが生かされている。厳選された国内産の栗を、保存上のギリギリまで甘さを抑えて仕込んでいるのが特徴だという。低糖度の糖液で蜜煮されたむき栗は、栗おこわ専用。缶詰の栗や瓶詰の栗などでつくる栗おこわでは決して味わえない優しい味だ。

1972(昭和47)年の誕生以来、多くのファンに愛されてきた「竹風堂」の栗おこわ。その秘訣は、餅米の蒸し方にまでこだわるところにある。餅米は蒸されると澱粉が糖化して甘みと旨みが出る。そのため、微妙な蒸し加減で、栗の持ち味と響き合う、腰があってソフトな食感の栗おこわに仕上げているという。

他にも定番の栗ようかんや栗のどらやきなど、小布施の老舗菓子店には様々な栗菓子が用意されている。どれを食べようか迷ってしまうほど。そして、シンプルに栗そのものの持ち味を味わいたければ、焼きたての焼き栗も魅力的だ。いずれにせよ、栗のシーズンになったら、一度は小布施に足を運んでみてほしい。