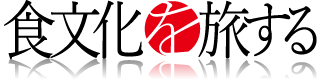北信地域の山間部は、畑の多くが急傾斜で、稲作には適していなかったため、麦を栽培し、米の代わりの主食としていた。加えて、稲作に適した千曲川流域の平坦地でも、水田の裏作として麦が多く栽培されていた。米は、貴重だったため、節約の意味で、信州では昔から、おやきなど小麦粉を使った「粉もの」が多く食べられていた。にらせんべいも、そんな「粉もの」のひとつだ。

おやきは、野菜などを入れ、中華まんのように厚手の生地でくるんで焼いたものだが、一方で、粉を水溶きして、その中に刻んだ野菜を入れて焼いたものを「せんべい」や「うす焼き」と呼んでいた。韓国のチヂミによく似た料理だ。ご飯とご飯の間の中間食であるおこびる(おこびれ)や子どものおやつに、このせんべいがよくつくられてきた。

ボウルにみそ、砂糖を入れてよく混ぜ、溶き卵、水を順に加えて混ぜ合わせる。そこに小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜたら、約1センチの長さに切ったニラを加える。サラダ油を敷いたフライパンに、これを流して広げる。ふたをして弱火で2~3分焼き、その後再び油を加え裏返して3分ほど焼けばできあがりだ。食べ方はいろいろで、家庭によって、味噌だれやしょうゆだれをかけて食べたりした。

ちなみに、おこびる(おこびれ)とは、「小昼(こひる)」が変化したもので、畑仕事の労働の間に食べるため、腹持ちのよいものが好まれた。中に入れる季節の野菜は、おやき同様、にらに限らずなす、ねぎなどがある。にらは栽培が簡単で、雪の積もる冬以外はいつでも収穫できることから、信州では、どの家でも庭先に植えいたという。

実際に長野を訪れて、にらせんべいを食べてみることにした。まずは、長野市穂保にある農産物直売所「JAながのアグリながぬま」を訪ねた。各地にある農協直営の農産物直売所だが、人気店のようで、午前10時の開店直後から、店頭の駐車場が満車という盛況ぶりだった。

ここのにらせんべいは、業者が焼いて持ち込んだもの。透明なプラスチック容器に入って販売されていた。大きく焼いたものをカットして小分けにしているようで、1食分、4カットがパッケージされていた。その特徴は、かなり厚手だ。まさにお好み焼きといった食べ応えのある厚みだった。

大ぶりに刻まれたニラが、厚みのあるせんべいの中でしっかりとその存在感を発揮している。そして味付け。表面に、甘めの味噌がしっかり塗り込まれている。今回食べたにらせんべいは味噌味のものが多かった。さすがに、味噌と言えば信州だ。やや焼きの温度が高いのか、しっかり気味の歯ごたえだった。

続いて訪れたのは、善光寺の表参道にある「門前農館さんやそう」だ。地元農家のお母さんたちが手作りしている、地元野菜を使ったおやきで人気のお店だ。ずらりと並んだおやきの一方で、やはりプラスチックの透明なパックに入ったにらせんべいが販売されていた。

一見すると、「JAながのアグリながぬま」のものと区別がつかないほど、そっくりのビジュアルだった。やはり大きく焼いたものをカットしているようで、四角く切られていた。厚みがあるのも同様だ。一方で、焼く温度が低めなのか、「JAながのアグリながぬま」よりもややソフトな食感だった。甘い味噌がたっぷりと塗られているのも同様だった。

次に向かったのが、長野市若穂にあるおやき屋「信濃製菓」だ。昭和30年代前半から和菓子、おやきの販売を始めたという老舗だ。当時「おやきは家庭で作るもので、売りものにはならない」といわれていたが、今では通信販売でおやきを届けるまでになっている。

「信濃製菓」では、特に春先に伸びた柔らかいにらでつくったにらせんべいは格別だと評判だ。にらせんべいやうす焼きのつくり方は家庭によって少しずつ異なり、粉と野菜と一緒に味噌も混ぜて焼いたり、焼き上がってから、味噌だれやしょうゆだれをかけて食べたりといろいろあるそうだ。「信濃製菓」では、薄く、小さな円形に焼かれていた。一見して、いかにも「せんべい」と呼べる形状だ。

味付けも、前出の2店とは異なっていた。甘さ控えめの味噌を2枚のせんべいではさんであった。薄めの分、食感も軽く。まさにおやつ感覚のにらせんべいだった。

最後に訪れたのは、2023年8月にオープンしたばかりの、テイクアウトのにらせんべい専門店「食の森ひつじ」だ。地元では、子供のおやつとして広く愛されてきたにらせんべいだが、おやきに比べると地味な存在だという。そこに着目して、にらにこだわらず、季節の野菜を練り込んで、現代風のにらせんべいを完成させた。

1枚150円という手頃な価格もあり、店のすべてのにらせんべいを食べてみた。オーソドックスなにらせんべいと七味唐辛子入り、しめじ、野沢菜、紅しょうが、そしてあずきだ。同店のにらせんべいは、予め焼き上げておいたせんべいを油を敷いたフライパンで温め直して提供している。油をまとうことで、よりソフトな食感になる。

これまでの3店とは違い、味噌は後塗りしない。紅しょうがや野沢菜が典型的だが、中に入れる素材の持ち味を上手に引き出す調理法だ。七味唐辛子入りはピリッとした辛さで、ビールのつまみにも適していると感じた。そして、注目はあずき。甘いのかと思いきや、甘さ控えめで、これもまた小豆の持ち味を引き出す味付けだった。

おやきほどの知名度こそないが、地元で愛され続けてきたにらせんべい。素朴な粉ものはどこかほっとする味だ。ご紹介したように、おやきを扱う店で一緒に売られていることも多いようだ。長野を訪れた際は、ぜひ探して食べてみてほしい。