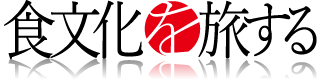初夏の訪れを告げる果実、びわ。元々日本でも自生していたが、江戸時代に、中国から伝わった品種の栽培が本格化、現在に至っている。県別生産量では、長崎県が全国生産量の24%、千葉県が20%、香川県、鹿児島県、愛媛県がそれぞれ7%と、西の長崎、東の千葉が、主産地と言っていいだろう。

千葉を代表する果物と言えば、梨を挙げる人が最も多いはずだ。しかし、梨は、市川や松戸、白井と言った県の北西部、内陸の平野が栽培の適所となっている。一方、山がちな、関東平野から外れたエリアが、逆にびわの主産地だ。特に南房総市は、長崎県の茂木(もぎ)と並び、びわの日本二大産地のひとつに数えられる。

びわというと、種が大きく、可食部分が少ないイメージだが、南房総で収穫される房州びわは、肉厚で、ジューシーな果実で知られる。一粒一粒の形が美しく、黄橙色の果皮も食欲をそそる。とくに果汁の豊富さは、かじると滴り落ちるほどで、甘さも上品なことから、初夏の限られた時期にしか味わえない果物の貴婦人として、全国で愛されている。

千葉県のびわ栽培は、1751(宝暦元)年頃に始待ったと言われており、270年以上の歴史を誇っている。また、房州びわは、1909(明治42)年に、安房郡富浦村南無谷(現南房総市富浦町南無谷)の木村兼吉(きむらかねきち)が皇室に献上。以来、第二次世界大戦中とコロナ禍に見舞われた2020-21年の一時期を除き、ずっと継続されてる。

びわはクエン酸やリンゴ酸などの有機酸を多く含み、カロチン(ビタミンA)に富んでおり、カロチンの含有率はピーマンやトマトを上回る。果実だけでなく、葉は古くから民間療法に用いられてきた。ビタミンC、ビタミンB、ポリフェノール、サポニンなどを多く含むため、動脈硬化、高血圧予防や疲労回復によいとされる。びわの薬効は、びわの木には多くの病人がそれを求めて集まることから「びわを植えると病人が絶えないので庭に植えてはならない」という迷信があるほどだ。

びわは、温暖な地の石灰岩地帯に自生する植物で、花が寒さに弱いため北海道や東北では栽培が難しく、適地は関東南部以西とされてきたが、近年は改良が進み、積雪のある地方でも対応できる品種が登場している。とはいえ、やはり主産地は温暖な土地だ。手間をかけずに収穫できることが、ビワの特長だが、間引きや袋がけをすればより大きな実を実らせることができる。枝は横へ横へと広がり、濃緑の葉がよく茂るため、放っておくと鬱蒼とするので、家庭栽培では定期的に剪定する必要がある。

そんな房州びわを味わうには、やはり南房総市を訪れるのがいい。おすすめは、富浦にある「道の駅とみうら枇杷倶楽部」だ。館山自動車道の終点・富浦インターチェンジを降りると目の前にあるのが「道の駅とみうら」だが、「枇杷倶楽部」は国道を右折して、海に向かって、内房線の線路を越えた少し離れたところにある。

ここでは、とれたての新鮮なびわを購入できるのはもちろん、びわの収穫体験、びわ狩りも楽しむことができる。「道の駅とみうら枇杷倶楽部」に隣接する「房総の蔵お百姓市場」で料金を支払えば、ワンボックスカーで近隣のびわの栽培場まで連れて行ってくれる。

びわは、害虫や強い日差しによるしみ・そばかすなどから果実を守るため、果実が小さいうちに生産者が1つひとつ袋をかけて大切に育てる。緑色の実が、熟すに従い、黄橙色を帯びて来て、より色が濃くなったら食べごろだ。しかし、袋がかかっているので、袋の先をちょっと破って中の色を確かめてからもぐようにする。

収穫する際は、花柄(かへい)と呼ばれる茎の部分を枝から折るのがルール。果実を花柄からもいでしまうと、翌年、実がならないそうだ。花柄ごと収穫したうえで、改めて、花柄を身から引きはがす。皮をむく際は、ヘタ側からでもかまわないが、反対お尻側からむくと、皮がむきやすい。

びわ狩りで最も美味しいとされるのは、完熟して自然落果したびわだ。完熟度が進んでいるため、出荷するまでに黒ずんでしまうのだという。とはいえ、落果直後に食べることができれば、最高に熟した状態で食べられるというわけだ。黄橙色も濃く、実もぐずぐずになるかならないかの食感だ。まるで干し柿のようにねっとりしていて、極上の甘さを楽しめた。

時間によっては、手の届く範囲の完熟びわがとりつくされてしまう懸念もあるが、予め収穫しておいたびわがかごに入れて置かれているので、心配は無用だ。もぐ手間を省いて、かごの中のびわをひたすらむいて食べ続けている人さえいたほどだ。その果肉の厚さとジューシーさには、正直なところ、びわに対する概念が変わったといっても過言ではない。

皮をむいて、かぶりつくと、そこから果汁がしたたり落ちるというか、噴出してくる。流れ出た果汁で、食べ進むうちに、手がべたべたになるほどだ。食べ放題が終わったら、手を洗わないと大変なことになる。

店頭には、何種類かの品種のびわが並んでいた。富房は、安定した品種で、糖度は11~12%で、酸度は低く食味がいい。輸送性も高く、日持ちも良いというメリットもある。なつたより 糖度が13.1~15.9%と甘く、実も大きく、粒揃いもいい。百科店や高級フルーツ店などで取り扱われる品種だ。

「道の駅とみうら枇杷倶楽部」へ行けば、びわを使ったスイーツやジュース、アイスなどがずらりと並ぶ。さらにレストランでは、隠し味に房州産びわピューレを使ったびわカレーも食べられる。

びわ狩りのシーズンは、5月上旬から6月下旬にかけてだ。5月はハウスのびわを、6月は路地のびわをもいで食べられる。ちなみに、「道の駅とみうら枇杷倶楽部」は、千葉県初の道の駅として1993年開業と歴史のある道の駅であるだけでなく、2000年には全国道の駅グランプリで最優秀賞を受賞している。一度は訪れておきたい施設と言える。